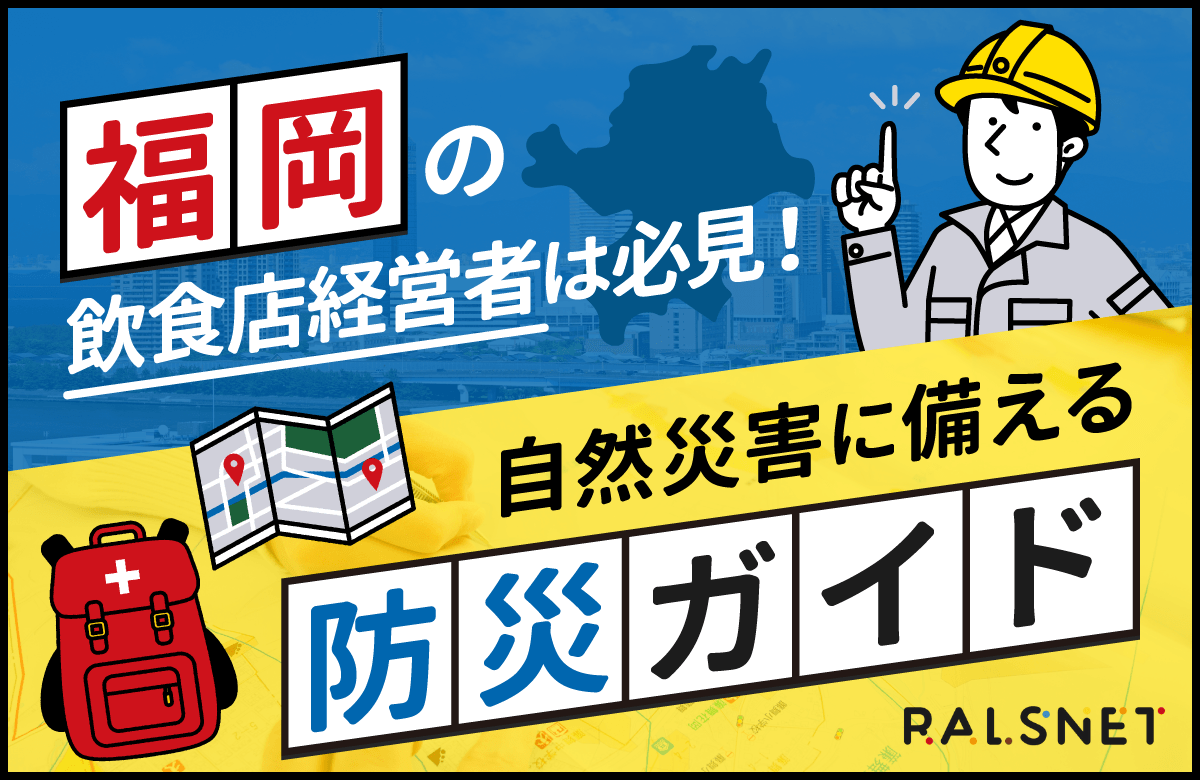福岡市は九州地方最大の人口を有し、多彩なグルメが楽しめる町です。飲食店の経営者にとって魅力の多い土地ですが、自然災害は日本のどこにいても起こりえます。
福岡市の災害リスクを把握し、飲食店でも防災対策を行いましょう。
本記事では、福岡市で飲食店を経営している人に向けて、過去の災害例や福岡市が提供している防災対策について解説しています。防災をお考えの際は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:あなたの店舗は安全ですか?出店者が知っておくべき災害対策と復旧手順
目次
飲食店でできる防災対策

福岡は豊富な食材が揃ううえに、郷土料理も多いため、飲食店の多い都市です。学生・ビジネスパーソン・観光客などさまざまな需要があり、人口1,000人当たりのレストラン数は大阪、東京に続く3位を誇ります。
しかし、日本では地震や水害などの自然災害が多く、店舗でも防災が必要です。福岡市で飲食店を経営している人もできる限りの対策をしましょう。
防災のポイントとして、次のようなものがあります。
- 福岡の防災対策を知っておく
- 火災対策
- ガラス対策
福岡の防災対策を知っておく
重要なのは、福岡市で提供している防災対策を把握することです。災害の情報や対応をいち早く得ることで、人命や店舗を守れる可能性が格段に上がります。
たとえば、福岡市では緊急情報や気象警報などの防災情報をメールで届ける「福岡市防災メール」のサービスを提供しています。
スマートフォンやパソコンなどへ事前に登録しておけば災害発生時にすぐ情報が得られるため、お客様を避難させるべきかなどの判断が可能です。
また、福岡市では防災情報のホームページを用意しています。災害や有事などの緊急情報だけでなく、日常で災害に備えるためのメニューも掲載されているので、普段から確認しておくと良いでしょう。
ほかにも、福岡市で提供している防災情報・ツールとして、次のようなものがあります。
| 防災情報・ツール | 内容 |
|---|---|
| 福岡市総合ハザードマップ | 洪水・土砂災害・地震などの災害による危険度情報を掲載 |
| 福岡市防災気象情報 | 台風や集中豪雨から身を守るために防災気象情報を提供するサイト。河川カメラ、水位計、雨量計による観測情報がリアルタイムで表示される |
| 福岡市防災マップ | エリアごとの避難所の詳細な情報のほか、避難時の心得などをまとめたサイト |
| 福岡市消防局 | 防火・防災・救急に関する講座や福岡市民防災センターの施設についての案内を掲載 |
| 福岡市LINE公式アカウント | 受信設定で防災・気象情報を設定できる |
| 防災アプリ「ツナガル+(プラス)」 | 避難所の場所や機能などの確認が可能 |
| 避難情報配信システム | 視覚・聴覚などに障がいがある方や高齢者などの避難情報の入手が困難な方を対象に、固定電話等の音声やFAXで情報を知らせるサービス |
店舗の住所にどのような災害リスクがあるのか事前に調べておくのはもちろん、防災メールや防災アプリに事前に登録し、できる限りの対策をしておきましょう。
参考:福岡市よくある質問Q&A
火災対策
コンロの火などで調理する飲食店は、地震発生時の火災に警戒・対策が必要です。まず、飲食店で義務付けられている防火対策に問題がないか確認しましょう。
2019年10月1日の消防法施行令の改正により、火を使う設備がある飲食店などでは延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。
飲食店では住宅用ではなく業務用の消火器の設置が必要です。誤って住宅用消火器を用意して買い直しになる事例もあるので、注意しましょう。
また、次のように、店舗の規模によって防火管理者の選任が必要です。
| 店舗規模 | 種類 |
|---|---|
| 収容可能な人数が30人以上で延べ面積300㎡未満 | 乙種防火管理者 |
| 収容可能な人数が30人以上で延べ面積300㎡以上 | 甲種防火管理者 |
防火管理者は不特定多数の人が集まる場所で火災を防ぐための責任者で、講習を受けて資格を取得します。甲種は約10時間、乙種は約5時間の講習です。
上記の条件に当てはまらない店舗では、防火管理者の設置は義務付けられていません。しかし、防災や火災対策を考えるなら、資格を取得するか同様の知識を身に着けておいた方が良いでしょう。このような火災対策は、災害発生時に有効です。
ほかにも、消火設備・警報設備・避難設備などの防火設備の定期的な点検も義務付けられています。
福岡市消防局では飲食店経営者やこれから飲食店を始める人に対し、次のような情報発信・注意喚起を積極的に行っています。
- 火災予防の講習会
- 排気ダクトの清掃
- 防火管理者の申請書・届出関連
- 定期点検などの案内
不明な点があれば、店舗の所在地を管轄する消防署(出張所以外)に確認してみてください。
参考:福岡市消防局
ガラス対策
地震や台風が発生すると、飲食店では窓ガラスや食器類が割れて飛び散る危険性があります。そのため、次のような対策がオススメです。
- 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る
- 防災用の窓ガラスに交換する
- 窓ガラスの周辺に植木鉢などの飛来物になりそうなものを置かない
- 目線より上に食器類を配置しない
- 木製やプラスチックなどの割れづらい食器を使う
台風や強風の情報は気象予報や福岡市の防災情報のホームページで確認し、事前にガラス対策を行いましょう。
一方、地震はいつ起こるかわかりません。重い食器やボトル類は低い場所に配置したり、滑り止めシートを使って落ちないようにしたりといった、普段からの対策が重要です。
福岡市のハザードマップ

災害に備えるためにも、ハザードマップは必ず確認しましょう。
「福岡の防災対策を知っておく」でも前述したように、福岡市で作成したハザードマップがあります。洪水・地震・土砂災害などの災害リスクが表示できるので、自店舗の住所や近隣を確認してみてください。
また、国土交通省が運営する、「ハザードマップポータルサイト」からも災害リスクの高いエリアを調べることが可能です。関連記事「あなたの店舗は安全ですか?出店者が知っておくべき災害対策と復旧手順」でもハザードマップの説明をしているので、ご覧ください。
リスクの高い災害を知ることで対策が可能になり、いざという時に避難などの的確な行動につながります。
福岡市で過去に起きた災害例

福岡市では過去に地震や豪雨を経験しています。災害の状況や被害について具体的な事例を見ていきましょう。
地震
福岡市では、2005年3月20日に福岡県西方沖を震源とするマグニチュード7.0の地震(福岡県西方沖地震)が発生しました。福岡市の下記の区で震度5以上の揺れを観測しています。
| 震度 | 地域 |
|---|---|
| 震度6弱 | 東区、中央区 |
| 震度5強 | 早良区、西区 |
| 震度5弱 | 博多区、南区、城南区 |
津波は観測されませんでしたが、全壊141棟、半壊315棟などの大きな被害をもたらしました。
福岡県西方沖地震は福岡市観測史上最大の地震です。2005年12月31日までに405回の余震が観測されるなど、地震の影響は長く続きました。
しかし、福岡県西方沖地震以外の大地震の記録はなく、「福岡市は大地震が少ない」とされてきました。とはいえ、将来的に大地震が発生しないとは言い切れません。
福岡市には警固断層(警固断層帯南東部)があります。想定されている地震規模はマグニチュード7.2です。ハザードマップでも福岡市街で震度6強以上の可能性が表示されています。
福岡県西方沖地震の影響によって発生する確率が上がったとも言われており、大地震への警戒は福岡市でも必要です。
参考:福岡市総合ハザードマップ
風水害
福岡市では下記のように、たびたび風水害が発生しています。
- 1999年6月 水害
- 2003年7月 水害
- 2009年7月 水害(平成21年7月中国・九州北部豪雨)
- 2010年7月 水害
- 2018年7月 風水害(平成30年7月豪雨・台風第12号)
1999年6月の水害は1時間最大雨量79.5mmの豪雨によってもたらされました。2003年7月にも1時間最大雨量104mmの豪雨により、博多駅地下街などの地下空間に雨水が流入する被害が発生しています。
福岡市は日本海型気候で、もともと6~7月は梅雨により雨が発生しやすい期間です。
しかし、近年の地球温暖化の影響により豪雨のリスクが高まっており、福岡県では1980 年前後と比較すると2020年の短時間大雨の年間発生回数は約1.7倍に増えています。
福岡市で水害の危険があるエリアで飲食店を経営するなら、洪水ハザードマップや河川の水位の確認はしておいた方が良いでしょう。
参考:九州災害履歴情報データベース
福岡市地球温暖化対策実行計画
福岡市は災害に強い?

福岡市では地震や豪雨など、何度か大きな自然災害が起きています。災害発生後の対応や、防災の取り組みについて詳しく見ていきましょう。
災害発生後の対応
福岡市は、福岡県西方沖地震発生の27分後には「福岡市災害対策本部」を設置し、被害の大きかった玄界島への自衛隊派遣の要請を福岡県を通じて行うなど、素早い対策を講じました。
2009年の水害では、住民から被害の報告を受けた市町の職員が現地へ派遣され、避難勧告・避難指示・自主避難を進めるなどの指示を出しています。また、過去に水害の経験があった地域では、地域独自で早めの避難を呼びかけるなど、スピーディーな対策をとっていました。
参考:第1節 災害対策本部の設置と初期活動 – 福岡市
福岡都市圏流域における2009年7月豪雨による水害の特性と行政機関・住民の対応
防災の取り組み
福岡市では、2016年に発生した熊本地震後、大地震への警戒を強め、食料・段ボールベッドなどの公的備蓄を拡充する対応を進めています。
水害に対しても、下水道の整備や公共施設での雨水流出抑制施設導入を進めるなど、さまざまな対策に取り組んでおり、水害リスクを減らしています。
2012年には、週刊誌「女性自身」に掲載された『大地震でも生き残る街「全国ベスト5」公開』では福岡市が首位に選ばれました。
理由として、次のようなものがあります。
- 過去に福岡市を中心とする大地震がない
- 非木造率が高く老朽化した建物が少ない
- 人口当たりの店舗数・商品販売数・医師の数が多い
過去の災害例や、生活の利便性などが理由の首位です。そもそも、福岡市は官民で防災に取り組んでいる都市です。
2015年から「天神ビッグバン」というプロジェクトによって、天神エリアの老朽化が進んだビルを、耐震性の進んだインテリジェントビルへと建て替えを進めています。
天神ビッグバンについては関連記事「天神で飲食店を開業したい!エリアごとの魅力とテナント物件の探し方」でも解説しているので、ご覧ください。
2022年には、災害時の本部体制強化を目的に本庁舎に新たな災害対策本部室を公開し、災害対応用のネットワーク回線を導入するなど危機管理に力を入れています。
また、同じく2022年には市立小学校に通う4~6年生を対象に民間企業とタイアップした小学生向け防災情報紙「もしも新聞」を配布し、福岡市役所・各区役所にも設置しています。
福岡市で災害が起こらないわけではありません。しかし、防災に力を入れており、災害発生時にも強い都市と言えるでしょう。
福岡で物件を探すならテナント連合隊を活用しよう!

福岡市は飲食店を経営する人にとって魅力の多い街です。
しかし、日本は自然災害が多く、福岡市でも過去に地震や大雨による被害が発生しています。飲食店を営む人にも防災対策は必須です。
福岡市の防災の取り組みを把握したり、防火管理者の設置・知識の習得をして火災に備えたりと、可能な限り対策をしておきましょう。
福岡市で防災を考えたテナント物件を探している方は、ラルズネットが運営する「福岡テナント連合隊」をご活用ください。
築年数や中央区・南区・博多区といった福岡市のエリアを指定して店舗用の物件を探すことが可能です。これから移転や出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。