飲食店を経営しているなかで、1店舗目の業績が安定してくると考え始めるのが、2店舗目の出店です。
飲食店の2店舗目を出店したい場合、「出店のタイミングはいつが良いのか」「どのように立地を選べば良いのか」と、疑問に思う方もいるでしょう。
2店舗目を出店する際は、特にタイミングが重要です。出店時に満たすべき条件を押さえておくことで、店舗拡大に伴う業績不振のリスクを軽減できるでしょう。
本記事では、飲食店の2店舗目を出店する適切なタイミングについて解説します。メリットや押さえるべきポイントについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
2店舗目の飲食店を出店する適切なタイミング

2店舗目の飲食店を構える際は、タイミングの見極めが重要です。
店舗拡大を図る前に、次のような条件を満たせているか確認しましょう。
- 既存店舗で安定して利益を出せている
- 十分な資金が準備できる
- 信頼できる店舗管理者が存在する
既存店舗で安定して利益を出せている
2店舗目を出店した場合、すぐに黒字化できるとは限りません。そのため、1店舗目で安定した利益を計上できているかを確認しましょう。既存店舗の利益が安定していれば、新しい店舗で赤字が出た場合でも補填が可能です。
また、店舗拡大に伴い融資を受ける場合、既存店舗の経営状態が融資の可否や上限額を決める指標になります。
1店舗目の売上が少ない、あるいは十分な利益を確保できていなければ、審査に落ちてしまう可能性も否定できません。仮に、融資を受けられたとしても、返済が負担になる場合もあるでしょう。
利益を増やすには、食材費・人件費の抑制やロス率の改善といった方法が効果的です。また、サービスの提供スピードを速め、メニュー数を最適化して回転率を高めるのも良いでしょう。
既存店舗で成果を上げれば、そのノウハウは新規出店時にも活かせます。
十分な資金が準備できる
2店舗目は新たな出店コストが発生するほか、人件費・食材費・賃料などのランニングコストも増えます。キャッシュフローが安定していても、十分な自己資金が確保できていないと、新規出店時のコスト増をカバーしきれない可能性があります。
新規出店に際して、日本政策金融公庫や民間の金融機関から融資を受けられますが、自己資本と他人資本のバランスには十分に配慮しましょう。月々の返済額が多ければ、新規出店によるランニングコストの増加が大きな負担となり、資金繰りが苦しくなるためです。
日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査(2021~2022年度)」によると、黒字かつ自己資本プラスの飲食店の平均自己資本比率は23.4%です。
まずは上記の平均値を参考に、綿密な資金計画を立てましょう。
信頼できる店舗管理者が存在する
複数の店舗を運営するには、店長や料理長といった店舗管理者が必要です。
単独の店舗であれば、経営者1人でも運営できるかもしれませんが、2店舗以降は話が変わってきます。複数店舗運営の場合、経営者が各店舗に常駐できないため、おのずと店舗管理を任せられる人員が求められるでしょう。
店舗管理者が不足していると、シフト作成や新人教育、発注業務などに手が回らず、サービス品質や従業員満足度が低下する可能性も考えられます。
必要十分な店舗管理者がいない場合は、既存店舗運営の早い段階で、人材の確保や社員教育を計画しておきましょう。
2店舗目の飲食店を出店するメリット

2店舗目の出店は、コスト面などでリスクが大きく、なかなか一歩が踏み出せない方もいるでしょう。
ただし、多店舗展開によって次のようなメリットが生まれるため、しっかりと準備を整えたうえで、思い切ってスタートを切るのも方法の一つです。
- 売上アップが期待できる
- 運営コストを削減しやすい
- リスク分散につながる
- 認知度が高まりやすい
売上アップが期待できる
店舗数が増えると収容客数も増加するため、売上の向上が期待できます。
また、店舗同士の距離が近い場合は、片方の店舗が満席状態でも、もう一方に案内できるため、機会損失を減らせるでしょう。
ただし、多店舗展開で仕入れルートが煩雑化し、原材料費の上昇によって利幅が狭くなる可能性があります。そのため、1店舗目との相乗効果を意識して出店場所を検討することが大切です。
運営コストを削減しやすい
一般的に食材や消耗品などは、一度に発注する量が多いほど、商品あたりの単価が安くなります。2店舗目の出店によって食材や消耗品などの発注量が増えると、仕入コストの削減につながるでしょう。
また、原材料費に限らず、人件費の削減も可能です。繁忙期などに既存店からヘルパーを派遣すれば、新規従業員の採用コストを削減できます。
多店舗展開による売上アップとコスト削減が上手く重なると、利益額の向上が見込めます。
リスク分散につながる
店舗が複数あると、一つの店舗が立ち行かなくなった場合でも、もう片方の店舗で赤字を補填できます。
飲食業のような領域では、外的要因によって営業不振に陥るケースが少なくありません。特に都市部では、新しい商業施設や競合店舗が次々と増えるなど、地方に比べて環境変化が活発です。
これらの環境変化によって人の流れが変わり、一時的に客入りが悪くなったり、新しい店舗に顧客を取られたりする可能性があります。その点、複数店舗を経営していると、業績が落ち込んだ店舗の損失をカバーできます。
また、2店舗を出店する際の成功・失敗体験を蓄積できるのもポイントです。多店舗運営のノウハウが増えれば、店舗経営全体のリスク抑制にもつながるでしょう。
認知度が高まりやすい
店舗数が多いほど店舗名やブランドロゴを見る人数が増えるため、認知度やブランディング効果を高めます。
特にオープン直後は、物珍しさに来店される方も多く、気に入ってもらえれば、口コミが広がることもあるでしょう。口コミが広がれば、認知度が高まるだけでなく、集客コストの削減も可能です。
また、複数店舗の存在は潜在的に顧客へと安心感を与え、新規顧客の獲得やリピートにもつながります。
特定の地域におけるシェアが高まれば、競合店舗の出店を抑える障壁となり、安定した売上を確保できます。
2店舗目の飲食店を出店する際に押さえておくべきポイント

2店舗の飲食店を出店する際は、気を付けるべきポイントがいくつか存在します。
失敗するリスクを軽減し、メリットを最大限に享受するためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 出店する業態は変えないほうが良い
- 新規出店の動機や経営理念を見直す
- 撤退条件を想定しておく
- 立地選びは慎重に行う
出店する業態は変えないほうが良い
2店舗目を出店する際は、1店舗目とは異なる業態で出店するケースもあります。しかし、業態を変えると、これまでのノウハウが十分に活かせない可能性があり、中長期的な業績を予測するのが困難です。
業態を変えて成功する場合もありますが、リスクが高まりやすい点には注意が必要です。
どうしても新規店舗に変化を加えたい場合は、業態を変えるのではなく、「当店限定メニュー」など、リスクが低く、来店を促進するような施策を考えると良いでしょう。
新規出店の動機や経営理念を見直す
多店舗展開では運営コストが高額になりがちです。新規出店後にあまりにもコストの負担が大きくなれば、既存店舗の運営にも支障を与えてしまいます。
そのため、経営者として多店舗展開によるリスクを負えるのかを、十分に検討することが重要です。
特に、新規出店の動機をしっかりと確かめておきましょう。
なかには、1店舗目の損失の穴埋めを理由に2店舗目を出店するケースもありますが、失敗に終わることも珍しくありません。損失が発生している要因を理解しないまま新たな店舗を出店しても、同じ失敗を繰り返す可能性が高いためです。
2店舗目をオープンする前に、新規出店の動機や経営理念を見直しましょう。
撤退条件を想定しておく
2店舗目を出店してから軌道に乗るまでには、ある程度の期間が必要です。その間に必要な費用は1店舗目で補填する必要があります。
とはいえ、既存店舗の利益で新規店舗の損失を穴埋めするには、限界があります。
そのため、「この期間までに○○円の利益が確保できなければ撤退する」といった条件を設定しておきましょう。
撤退条件を想定しておくと、今後の経営への影響を最小限に抑えられます。また、失敗した場合を想定して資金計画を立てられるため、仮に多店舗展開が上手くいかない場合でも、冷静に方針転換が可能です。
立地選びは慎重に行う
2店舗目の立地は1店舗目との距離が重要です。
店舗間の距離が遠すぎると、行き来するのに手間がかかります。その分、店舗運営の実態をつかむのが遅れたり、管理者との間でコミュニケーション不足が発生したりする可能性があります。
一方で、店舗間の距離が近すぎるのも問題です。すぐ近くに複数の自店があると、店舗同士で顧客を取り合うカニバリゼーションが生じるためです。
そのため、店舗同士は遠すぎず、近すぎない距離を意識しましょう。
そのほか、店舗間の距離だけでなく、その地域にターゲットとなる潜在顧客がいるか調査することも大切です。競合店舗との関係や周辺環境などによっても、安定的な売上が見込めるかを左右します。
立地や距離を意識して2店舗目の物件を探そう

2店舗目の飲食店を出店する際は、適切なタイミングを見極めましょう。1店舗目の利益が安定している、十分な資金がある、信頼できる店舗管理者がいるのであれば、比較的安心して多店舗展開を図れます。
また、物件を探す際は、立地や既存店との距離を意識することが大切です。競合関係やターゲットとなる顧客層の有無などを考慮しつつ、2店舗目に最適な物件を選びましょう。
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。

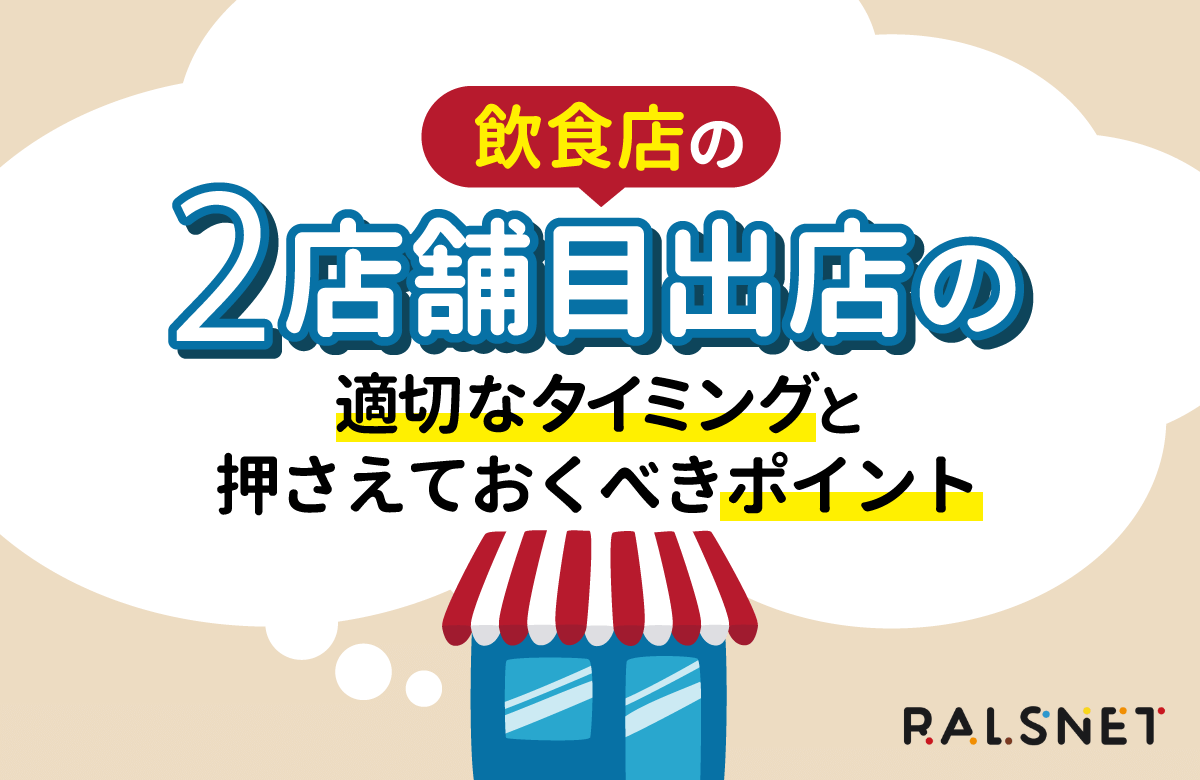



 で
で