日本政策金融公庫の「2022年度新規開業実態調査」によると、開業資金の平均値は1,077万円です。さらに、開業時に用意している自己資金の平均値は271万円と、資金調達手段の全体を通して約2割を占めています。
このような結果から、開業時にはある程度の自己資金を確保しておくべきだといえますが、開業資金ゼロでも飲食店を始められるのでしょうか。
本記事では、開業資金ゼロで飲食店をスタートするリスクや注意点を解説します。また、少ない予算でも可能な資金調達方法を解説していますが、飲食店を始める際は、なるべく潤沢な自己資金を準備しておくことが大切です。
目次
飲食店は開業資金ゼロでも始められるのか?

事実上、飲食店は開業資金ゼロでもスタートできます。しかし、開業時の自己資金が少ないほど、資金調達や事業運営で不利な立場に陥りやすい点には注意が必要です。
自己資金を用意せずに開業するのはおすすめできない
結論からいえば、自己資金をいっさい用意せずに開業するのは、リスクが高まってしまう点からおすすめできません。
本来、飲食店の開業には、物件の取得費や設備購入費、内装工事費といったさまざまな費用が発生します。この際に開業資金がなければ、何らかの方法で資金を調達しなければなりません。
しかし、自己資金ゼロで金融機関や公的機関から融資を受けるのは困難です。
また、飲食店を経営する際は、初期費用だけでなく、継続的に発生する運営コストを用意しておく必要があります。自己資金比率が低い、あるいはゼロやマイナスの場合、運営コストを利益でカバーしきれず、持続的な店舗経営が難しくなる可能性も考えられるでしょう。
そのため、開業までに十分な準備期間を設け、ある程度の自己資金を確保することが重要です。
営業形態によっては開業資金を抑えられる
多額の開業資金を用意できない場合は、営業形態を再考するのも方法の一つです。
例えば、テイクアウトやデリバリーのみを提供するゴーストキッチンは、一般的な飲食店に比べて開業時の初期費用を抑えられます。ゴーストキッチンでは、客席を用意する必要がなく、小規模なスペースでも事業を運営できるためです。
そのほか、車両で食品を提供するキッチンカーや、一つの店舗を複数の事業主で運営するシェアキッチンなどの選択肢もあります。
開業に必要な費用を最小化できれば、自己資金が少なくても、よりスムーズな資金調達が可能です。
開業資金ゼロで飲食店を始める方法

どうしても開業資金ゼロで飲食店を始めたい方は、次のような方法を参考にしてみてください。それぞれの手段は個別に活用できるだけでなく、複数を組み合わせることも可能です。
- 日本政策金融公庫からの融資
- 信用金庫からの融資
- 制度融資
- カードローン
- 第三者からの出資
- クラウドファンディング
- 資産の現金化
- 家族や知人からの支援
日本政策金融公庫からの融資
日本政策金融公庫では、個人事業主や小規模事業者でも利用しやすい、幅広い種類の融資制度を提供しています。
なかでも「創業時支援」は、自己資金ゼロで融資を受けられる可能性があります。
創業時支援とは、無担保・無保証人で資金を借りられる、創業者向けの融資制度です。下記の融資条件に当てはまる方は検討してみてはいかがでしょうか。
| 融資条件 | 融資制度 | 融資限度額 |
|---|---|---|
| 新たに事業を始める方またはおおむね事業開始後7年以内の方(生活衛生関係等の一部業種を除く) | 新規開業資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 生活衛生関係の事業を創業する方、または創業後おおむね7年以内の方 | 生活衛生新企業育成資金 | 振興計画認定組合の組合員の方:設備資金 1億5,000万円~7億2,000万円運転資金 5,700万円振興計画認定組合の組合員以外の方:設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
| 創業等に取り組む中小企業・小規模事業者であって、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果が見込まれる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方 | 資本性ローン | 7,200万円(別枠) |
ただし、上記の条件を満たしても、必ずしも融資を受けられるわけではありません。創業計画書や明確な事業計画書を作成し、計画遂行の能力があると判断される必要があります。
信用金庫からの融資
事業運営の実績がなく、なおかつ自己資金がゼロの状態で金融機関からの融資を受けるのは、現実的とはいえません。一般的に金融機関の融資サービスは、厳格な審査基準が設けられているからです。
一方、信用金庫の信用保証付き融資であれば、開業資金が少なくても融資を受けられる可能性があります。
信用保証付き融資とは、信用保証協会などが保証人となり、万一の返済トラブルの際に代位弁済を行ってくれる融資サービスです。金融機関にとっては貸し倒れリスクが大幅に軽減されるため、一般的な融資に比べて審査要件が緩和されます。
例えば、東京東信用金庫では、無担保で最大3,000万円の信用保証付き融資を提供しています。必ずしも自己資金ゼロで融資を受けられるわけではありませんが、試しに相談しておいて損はありません。
制度融資
制度融資とは、自治体・金融機関・信用保証協会の3つの機関によって生み出された融資制度です。
中小企業や個人事業主の創業・事業運営をサポートする制度が多いため、少ない開業資金でも融資を受けられる可能性があります。
例えば、東京都には「創業」という名称の制度融資が存在します。具体的な制度内容は次の通りです。
| 対象者 | 【以下のいずれかに該当すること】 ・現在事業を行っておらず、創業に向けた具体的な計画を持っている個人 ・創業日から5年未満の中小企業 ・分社化を予定している、または分社化による設立日から5年未満の企業 |
| 融資金額 | 最大3,500万円 |
| 返済期間 | ・設備資金:10年以内 ・運転資金:7年以内 ※据置期間1年以内を含む |
※2023年12月に執筆した記事です。最新情報は東京都創業NET|東京都中小企業制度融資「創業」をご確認ください。
カードローン
カードローンは、銀行系と消費者金融系の2種類に大別されます。特に消費者金融系カードローンは、比較的審査が緩く、自己資金なしで資金を借りられるケースも珍しくありません。
ただし、カードローンでは高水準の金利に注意しましょう。
例えば、消費者金融大手のアコムの場合、年利は3~18%です。借入金額が少ないほど水準が高くなります。借入限度額は800万円ですが、上限は審査によって決定するため、希望額が必ず反映されるとは限りません。
カードローンを利用する際は、このような点に配慮しつつ、綿密な返済計画を立てることが大切です。
参考:アコム|カードローン
第三者からの出資
もし、新規性が高く魅力的な事業を始める場合は、第三者からの出資を検討するのも方法の一つです。
融資のような借入金は負債となりますが、出資を受ける場合は資本扱いとなります。原則として返還の義務を負わないばかりか、自己資本として扱われるため、財務体質の強化につながるのが利点です。
第三者からの出資には次のような種類があります。
- 社員持株会での共同出資
- 他企業からの出資受入
- ベンチャーキャピタル(VC)からの出資受入
- エンジェル投資家からの出資受入
ただし、このような方法を活用するには、第三者が資金を提供しても良いと思えるような事業の独自性が必要です。
クラウドファンディング
クラウドファンディングも第三者から出資を募る方法ですが、インターネット上で広く情報を発信できる特徴があります。
具体的には、次のような手順で出資を募ります。
- クラウドファンディングのプラットフォームに登録する
- 目標金額や出資者へのリターンを考える
- プロジェクトを登録し、プラットフォーム運営者側の審査を受ける
- 定期的に出資者への活動報告を行う
- プロジェクト終了後、出資者へリターンを提供する
ここで注意すべき点は目標金額の達成可否です。
クラウドファンディングは原則として、出資総額が目標金額に到達しないと支援金を得られません。そのため、投資家にとって魅力的なプロジェクトや、価値あるリターンを考える必要があります。
資産の現金化
現在保有している資産を売却し、開業資金の一部に充当するのも良いでしょう。既存の資産を利用することから、「アセットファイナンス」とも呼ばれています。
売却できる資産は、不動産や設備、車両などのほか、特許権などの無形資産も含まれます。
買い手さえ見つかれば、迅速に資金を調達できますが、資産の売却だけで開業資金のすべてをまかなうのは難しいものです。そのため、融資や出資などの手段もあわせて検討しましょう。
なお、アセットファイナンスには、資産の売却以外にも次のような方法があります。
- ファクタリング(売掛金の現金化)
- M&A・事業譲渡
- リースバック(物品売却と同時にリース契約へ移行)
家族や知人からの支援
飲食店の開業資金を用意するには、家族や親戚、知人から資金を借りる、あるいは贈与を受ける方法も活用できます。
資金を借りる際は、金融機関からの融資とは対照的に、金利や返済期間の融通が利きやすいメリットがあります。
ただし、開業資金の全額を調達するのは現実的に困難です。前述の通り、飲食店を開業する際は、1,000万円ほどの資金が必要になるケースもあるからです。
また、贈与を受ける場合、贈与税が発生する可能性がある点にも注意すべきでしょう。
過度な期待はせず、ほかの手段と組み合わせて資金調達する算段を立てておくのがおすすめです。
飲食店の開業資金を調達する際の注意点

ここまで複数の資金調達方法をお伝えしましたが、それぞれに共通する注意点が存在します。
よりスムーズな資金調達を実現するためにも、次のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
- 自己資金の定義を理解する
- 資金調達の手段ごとに優先順位を付ける
- 調達した資金を事業以外の用途に使用しない
自己資金の定義を理解する
金融機関や公的機関などから融資を受ける場合は、原則としてある程度の自己資金が必要です。そのため、自己資金として認められる範囲を理解しておくことが重要です。
一般的に次のようなものは、自己資金として認められる可能性が高いでしょう。
- 入出金履歴が確認できる預貯金
- 退職金
- 保険の解約返戻金
- 贈与金や相続金
- 自己資産の売却金
- 第三者からの出資金
一方、入出金履歴が確認できないタンス預金は、所有者を特定できない点から、自己資金としては認められません。そのほか、返還義務がある借入金は、金融機関や親族などの借入先にかかわらず、自己資金として扱われないので注意が必要です。
資金調達の手段ごとに優先順位を付ける
ここまでに紹介した計8つの資金調達手段は、大きく次の3類型に分類できます。
- デッドファイナンス:返還義務が生じる融資全般
- エクイティファイナンス:返還義務のない出資
- アセットファイナンス:資産の現金化
上記のうち、事業運営上、最も負担となるのはデッドファイナンスです。デッドファイナンスは会計上で負債として扱われ、返還義務が生じるため、調達金額によっては経営を圧迫する恐れがあります。
一方、返還義務のないエクイティファイナンスは、比較的負担が少なく、可能であれば優先的に活用したいところです。
このようにそれぞれの手段で負担の大小が異なるため、優先順位を明確にしつつ、適切な資金調達方法を検討しましょう。
調達した資金を事業以外の用途に使用しない
手段にかかわらず、調達した資金は必ず事業目的で使用しましょう。
例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度は、事業開始後の設備資金および運転資金として用途が定められています。
事業以外の用途に資金を使うと、調達先からの返還要請や差止請求が行われる可能性があります。調達資金の全部ではなく、一部を別の用途に使用するのも避けるべきです。
このような資金調達後のトラブルを避けるには、あらかじめ調達資金の用途を明確にしておくと良いでしょう。
飲食店を始めるなら計画的に開業資金を準備しよう

今回紹介した通り、開業資金ゼロで資金を調達する手段には、複数の選択肢が存在します。
しかし、自己資金がなく、他社からの借り入れが多くなってしまえば、事業開始後の運営コストが大きな負担となり、資金繰りが苦しくなる可能性も考えられるでしょう。そのため、開業までの期間に余裕を持って、なるべく多くの開業資金を用意することが大切です。
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。

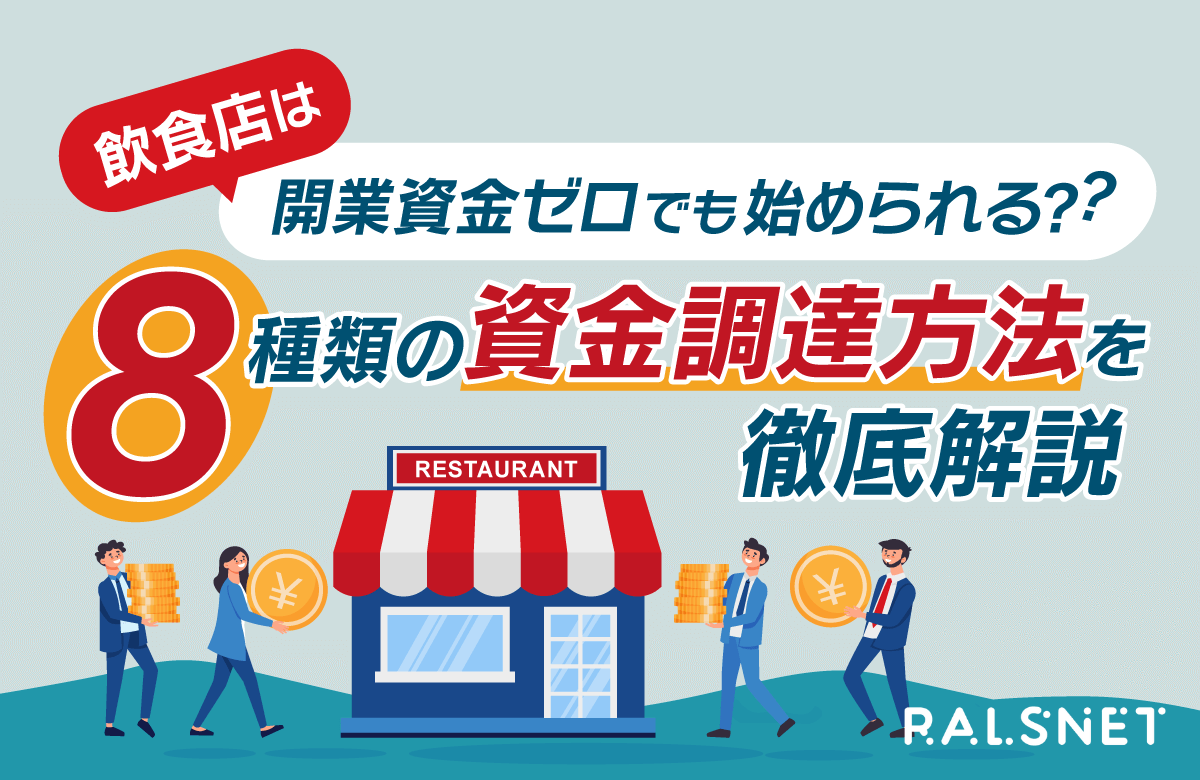



 で
で