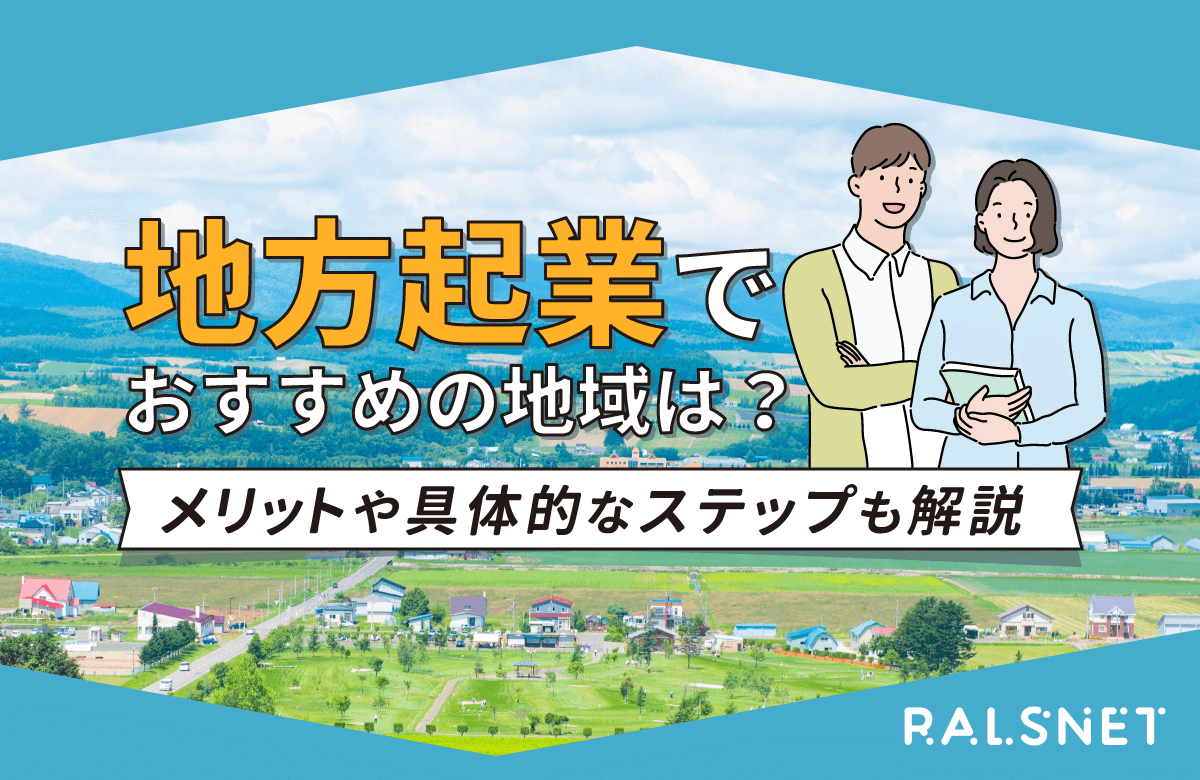地方移住とともに昨今注目を集めている地方起業。
地方にはその地域特有の特産物や環境など、魅力のある資源であふれています。地方での起業を考えている方のなかには、「おすすめの地域はある?」「具体的に何から始めれば良い?」と悩んでいるケースも多いのではないでしょうか。
準備に時間をかけ過ぎないためにも、おすすめの地域や起業するステップをある程度把握しておくことが大切です。
本記事では、地方起業のメリットやおすすめの地域、具体的なステップについて詳しく解説しています。起業に関する支援制度についても紹介していますので、地方起業を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
地方起業が注目を集めている背景

地方起業が注目を集めているのは、コスト削減や地方の資源を使って優位性を得たい企業が徐々に増えているからです。また、地方活性化のために企業誘致を積極的に推進する自治体が増えたことも、要因の一つだといえます。
昨今の日本では少子高齢化が問題視され、特に地方では首都圏への一極化の影響もあり、より深刻な状況が続いています。
これを防ぐためにも、地方創生の一環として創業支援を押し出している自治体が増えています。起業家が集まりベンチャー企業が増えれば、地域経済の活性化や雇用の創出につながり、人口の流出を抑えられるためです。
また地方では、都市圏に比べて最低賃金や家賃などのコストが低く、競合の数も少ないため、企業にとってもメリットがあります。
地方起業のデメリット

多くの企業から注目を集めている地方起業ですが、デメリットも存在します。
地方起業で注意すべき点を把握し、あらかじめ対策を講じると良いでしょう。
人材の確保や新規顧客の開拓が難しい
地方はもともとの人口が少ないため、高度な知識や技術を持つ人材が見つかりにくい傾向があります。
特に若い人材は首都圏に流出しがちです。人材の確保は、その地域でよく利用されている求人媒体をリサーチして余裕を持って取り組む必要があります。クラウドソーシングなどを活用して業務委託するのも一つの手段でしょう。
また、人口の母数が少ないということは、マーケットボリュームが小さいことを表しています。新規顧客の開拓や販路拡大の機会が都市部に比べて少なく、思うような業績につながらない可能性もあります。
しかしランチェスター戦略など、狭い地域のなかでもトップシェアを目指せる方法もあることから、必ずしも人口の少なさがマイナスに働くわけではありません。
業種によっては参入障壁が高い
地方では、既存の企業が市場を独占している業種もあり、参入障壁が高くなってしまう可能性があります。伝統ある企業が地域と深く結びついており、市場占有率が高い場合ほど新規参入が難しいでしょう。
地域住民にとって親しみのある既存企業が街のなかにあると、参入しても受け入れてもらえない、よそ者扱いを受けてしまうことも考えられます。
地方起業を考える際は、参入したい業界の動向や競合他社の地元定着具合をしっかりとリサーチしておくことが大切です。
通信環境や交通環境に配慮する必要がある
地方によっては、通信環境が悪かったり、近くに駅がないことで移動が不便だったりする可能性があります。
特に山間部では、インターネットにつながりにくく、通常業務に支障が出ることも珍しくありません。
また、交通環境が悪いと、通勤はもちろん出張時などの移動に時間がかかり、従業員がストレスを抱えてしまうこともあります。
地方は都会以上に、通信環境や交通環境に配慮する必要があるでしょう。
地方起業のメリット

地方起業は企業にとってさまざまな恩恵をもたらします。
ここでは、地方起業の代表的なメリットを紹介しますので、どのような効果が得られるか事前に検討してみてください。
初期費用・ランニングコストが抑えられる
地方では、都市圏に比べて人件費や家賃などのコストが低くなる傾向があります。
また、自治体によっては、起業に関する支援金や事業継続に役立つ補助金などの支援制度が充実していることもあり、初期費用やランニングコストを低く抑えることが可能です。
ただし、自治体の支援を受ける条件として、代表者自身がその地方に移住しなければならないケースがほとんどです。
プライベートでの生活の利便性も意識しつつ、起業先の地域を慎重に検討する必要があります。
顧客が奪われにくい
地方は都市圏に比べて人口が少ないからこそ、企業の総数が限られている地域も珍しくありません。競合の数が少ない分、一度獲得した顧客を他社に奪われるリスクが低いでしょう。
中小企業が中心となって地域経済を回しているケースも多く、起業したばかりの企業でも十分に太刀打ちできる環境が整っています。
前述したように、業種によっては新規参入が難しい地域もありますが、辛抱強く地元に馴染んでいくことで、盤石な経営体制を構築しやすいのが地方起業の大きな利点です。
未開拓エリアに参入したり、独自性の高い製品を投入したりといった工夫を凝らせば、小さなマーケットでトップシェアを狙えるチャンスが生まれます。
地域の特性や資源を活かしてビジネスができる
それぞれの地方には異なる特性や独自の資源があります。
特産品や名産品、伝統工芸品など、地域それぞれの資源を活かしてビジネスを展開すれば、より付加価値の高いブランディングにつながるでしょう。
さらに地方の課題を解決するようなビジネスを展開することで、地域住民からの支持を獲得でき、事業拡大にも発展可能です。
地域特有のネットワークを活かせる
多くの地方では、起業家同士のコミュニケーションが活発で、商工会による積極的な支援が行われています。横のつながりが強いという点が地方の魅力です。
地域特有のネットワークを活かすことで、事業運営コストの削減や新たなビジネスチャンスの発見につながることもあります。
例えば、栃木県佐野市にあるメーカーでは、地元にある複数の企業と連携して案件獲得を進めています。デジタルでスムーズな情報共有を実現しつつ、それぞれの弱みを補いながら製造に取り組むことで、競争力の強化につなげています。
参考:METI Journal ONLINE|地域に根付いたネットワークでモノづくりを展開
地方で起業する具体的なステップ

起業においては、事業継続にリソースを集中することが何よりも重要だといえます。
起業そのものに労力をかけないためにも、地方で起業する具体的なステップを把握しておきましょう。
地方で起業する目的を明確にする
起業を成功に導くには、強い意志と行動力が必要です。そのためにも、自分は起業して何を成し遂げたいのか、起業する目的を明確にしましょう。
起業する目的が明確になっていなければ、トラブルが起こった際の軌道修正が難しくなります。また、事業を続けていく意志が持続しづらいのも難点です。
それまでの実績や経歴を無駄にしないためにも、さまざまな視点から事業目的を掘り下げ、何があっても揺らぐことのない確固たる軸を構築しましょう。
地域の課題やアイデアをまとめる
せっかく地方で起業するなら、地域に根差したビジネスを展開したいところです。
まずは、起業先の地域にどのような課題があるのかを洗い出しましょう。日常生活で不便に感じることや街中を周って気付くことなど、地方で暮らす人々や自治体・行政機関から意見を集め、その地域特有のニーズを探ることが大切です。
そして、地域特有の課題やニーズを解消するためのアイデアを出します。「誰に・何を・どのような手段で提供するのか」、5W1Hの法則に沿ってビジネスプランを構築すると良いでしょう。
アイデアに行き詰まったり、ビジネスプランを考えるうえで課題が見つかったりした際は、自治体や同じ地域の事業家に助けを求めるのも一案です。
事業計画書を作成する
事業アイデアやビジネスプランが固まった後は事業計画書を作成します。
必ずしも事業計画書を作成する必要はありませんが、自治体の支援制度や金融機関からの融資を受ける際に提出が求められるため、事前に作成しておくことをおすすめします。
事業計画書には、主に次の内容を記載します。
- 創業者のプロフィールや経歴
- ビジョン・理念・事業目的
- 事業内容
- 商品・サービスの強みや特徴
- 市場環境・競合他社の動向
- 営業戦略やマーケティング戦略
- 仕入戦略や生産方法
- 売上や利益に関する計画・シミュレーション
地方起業に必要なものを揃える
事業計画書を作成したら、事業資金や人材、オフィスなど、起業に必要なものをそろえましょう。
起業してすぐに収益が発生するとは限らないため、少なくとも事業運営に必要な3~6か月分のランニングコストを、開業資金として用意するのがおすすめです。
また、起業先の地域はオフィスの賃料を加味して選ぶと良いでしょう。なかでも北海道は、都市圏に比べて土地代が安く、開業資金を抑えたい方に向いています。
起業手続きをする
企業を設立する場合は法務局で登記申請を行います。
登記申請で必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書・登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書・取締役の印鑑証明書
- 企業が使用する印鑑の届出書
- 資本金の払い込みを証明する書面
- 登記すべき事項を記載した書面やCD-R
ほかにも、税に関する手続きは税務署で行い、各都道府県の税事務所にも届け出が必要なので、忘れずに行いましょう。
地方起業に関する公的支援制度

地方起業を行う際は、国や公的機関から提供されている支援金や融資制度を活用してみてはいかがでしょうか。
支援金の場合は開業資金を捻出する負担を軽減でき、公的機関の融資は、一般的な金融機関よりも金利が優遇されています。
起業支援金|内閣府地方創生推進事務局
起業支援金とは、起業後の事業運営に必要な資金の一部を助成する制度です。内閣府地方創生推進事務局が提供している企業支援金は、最大200万円が受け取れます。
対象地域は東京圏以外の地域。東京圏で起業する場合でも、条件不利地域(奥多摩町や八丈町など)の場合は支援金の対象となります。
そのため、都市圏ではなく地方での起業を考えている方にとって、活用しやすい制度だといえるでしょう。
対象となる事業分野には、地域の特産品を使った飲食店や子育て支援など、その地域の課題解消につながるビジネスが中心です。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は内閣府地方創生推進事務局|起業支援金をご確認ください。
新規開業資金|日本政策金融公庫
新規開業資金は、新たに事業をはじめようとしている方や、事業開始から約7年以内の方を対象に、低金利で資金を融資する制度です。条件次第で0.1%程度の好条件で資金を調達できます。
なかには、Uターンなどで地方起業を行う場合や、「地域おこし協力隊」として活動した地域で起業するケースなどが条件に含まれていることから、地方でビジネスを行いたい方には便利な制度です。
融資限度額は最大7,200万円。設備資金は最長20年、運転資金は最長10年の借り入れ期間を設定できます。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は日本政策金融金庫|新規開業資金をご確認ください。
地方起業におすすめの地域

起業先の地域を選ぶ際は、自治体が提供している支援制度の充実度を一つの検討要素にすると良いでしょう。
ここでは、起業支援が充実している3つの自治体をご紹介します。
女性への起業支援も行う札幌市|北海道
北海道札幌市では、地方起業を考えている方や創業して間もない方を対象にさまざまな支援を行っています。
なかでも女性起業に対する支援制度が特徴的です。起業を子育てや介護などとの両立を図る手段の一つとして捉え、女性起業家同士の交流会や相談窓口、セミナーなどが用意されています。
また、札幌市の市街地には繁華街が栄えており、飲食店や小売店の出店に向いています。市街地から少し距離が離れると、豊かな自然が広がっているため、休日は落ち着いた環境でリラックスしたい方におすすめです。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は札幌市ホームページ|創業予定の方、創業間もない方への支援をご確認ください。
起業に関する支援や融資が豊富な長野市|長野県
長野県は、「日本一創業しやすい県づくり」をコンセプトに掲げており、充実した起業支援に特徴があります。なかでも長野県の県庁所在地で、中核市にも指定されている長野市は、起業に関する支援や融資が豊富です。
例えば、先輩創業者や社会保険労務士、経理コンサルタントなどの専門家が質問に答えてくれる「伴走型創業支援創業フォローアップデスク」や、ビジネスアイデアを構築したい方向けの「長野市実践起業塾」などが代表的です。
ほかにも起業時の補助金や融資制度が設けられており、開業資金を最小限に抑えられます。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は長野市ホームページ|長野市の創業支援についてをご確認ください。
開業率No.1※の街である福岡市|福岡県
福岡市では、企業を設立する際に必要な登録免許税を補助する「特定創業支援等事業」や、気軽に起業相談ができる「スタートアップカフェ」など、独自の支援制度が豊富です。
開業率は全国ナンバーワンの実績を誇り、それだけ起業家の方に人気がある地域だということがわかります。
※開業率は福岡市経済観光文化局が公表する2023年時点の実績(21大都市が対象)
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は福岡市ホームページ|創業(スタートアップ)をご確認ください。
関連記事:福岡市に移住する魅力とは?おすすめエリアや補助金制度を紹介
地方に移住して起業するなら北海道がおすすめ

地方起業は、自治体と企業双方にとって大きなメリットをもたらします。多くの自治体では企業向けの支援制度を提供しているため、最大限に活用することをおすすめします。
さまざまな自治体があるなかで、地方起業をするなら北海道への移住を検討してみてはいかがでしょうか。
北海道には、起業や新規就農を後押しする支援制度が豊富に用意されているため、地方起業の候補地をお探しの方は、ぜひ検討してみてください。以下の記事では、北海道のなかでも移住先として特に人気のある地域を紹介しています。