店舗の開店やオフィスの新設にあたって必要なテナント契約。
他地域への引っ越しなどで、居住用の賃貸借契約なら交わした経験がある方も多いでしょう。一方、「テナント契約は初めてで、何から手を付けて良いかわからない」というケースも少なくありません。
開業後の物件に関するトラブルや、余計な支出を極力なくすためにも、テナント契約時の注意点を理解しておくことが重要です。
本記事では、テナント契約をする際の注意点を6つのポイントに分けて解説します。よくありがちなトラブル事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
テナント契約する際の注意点

テナント契約を行うにあたって、各種書類や費用など、注意すべき複数の要素があります。契約後のトラブルに発展しないよう、必ず押さえておきましょう。
- 賃貸借契約書を詳細までチェックする
- テナント契約で必要な費用を確認する
- 退去時の原状回復について詳細を確認する
- 契約前の物件状態を確認しておく
- 物件の用途を説明する
- 敷金が返却されるか確認する
賃貸借契約書を詳細までチェックする
テナント契約時は、物件の情報や契約内容を書面に残し、不動産会社から重要事項説明を受けます。重要事項説明では、主に支払日や支払先、物件の引渡し時期などが書類に明記されています。
その際、重要事項説明と賃貸借契約書の内容に、齟齬や漏れがないか確認しましょう。特に、特約内容には、オーナーが有利になるような条件が記載されている可能性もあるため、要注意です。
また、細かい部分は無視して、重要なポイントのみを話す不動産会社やオーナーも存在するため、必ず詳細までチェックしましょう。
賃貸借契約には、「普通建物賃貸借契約」「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。契約の種類によって契約期間や更新時の注意点が異なるため、契約形態を明らかにすることが大切です。
普通建物賃貸借契約とは
普通建物賃貸借契約とは、契約期間の満了時に自動で契約が更新される、一般的な契約形態です。契約を終了する際は、借主と貸主の一方が更新拒絶の旨を通知しなければなりません。通知がなければ法定更新が適用され、法の下で契約が更新され続けることとなります。
契約更新手続きの手間を省けるため、中長期的なビジネス展開に向いています。
定期建物賃貸借契約とは
定期建物賃貸借契約は、満了日を迎えると自動的に契約が終了する契約形態です。そのため借主は、契約満了時に退去するか、貸主との間で新しい条件に合意したうえで再契約を結ぶ必要があります。
主に建物の建て替えや内装の修繕などで、一定期間だけ物件を貸したい場合に用いられます。
貸主にとって有利な契約形態だからこそ、普通建物賃貸借契約に比べて賃料が安く設定されているケースもあります。しかし、中長期的なビジネス展開を行う場合には不向きです。
テナント契約で必要な費用を確認する
テナント契約で必要な費用は次の通りです。
- 敷金(保証金):
一般的に賃料の10〜12ヶ月分を貸主に預ける。退去時に原状回復費用や未払賃料などが差し引かれ、敷金の一部が返還される。近畿・中国地方などの一部エリアでは保証金と呼ばれている。
- 礼金:
貸主に対して契約のお礼として支払う費用。法令で定められていないため、貸主に返還義務はない。一般的に賃料の1〜2ヶ月分が相場。契約する物件や地域によっては、礼金が発生しないこともある。
- 前家賃:
前もって支払う入居当月と次月の賃料。
- 共益費:
オフィスビルなどの共用スペースを管理するための費用。
- 仲介手数料:
不動産会社に支払う費用。「賃料の1ヶ月分+消費税」の上限が決まっている。
- 各種保険料:
テナント契約時に加入する保険の費用。
テナント契約に必要な費用は、不動産会社や物件によって異なります。把握漏れによって費用が予算を超えることがないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
関連記事:テナント契約の初期費用はいくら?項目ごとの相場や安く抑えるコツを解説
退去時の原状回復について詳細を確認する
原状回復とは、契約を解消して物件を返す際、契約前の状態に戻す義務のことを指します。
原状回復では、「契約前から付いていた傷を修復するよう要求された」「壁紙を新品に変えるよう求められた」などのトラブルがよく起こりがちです。このような注意事項は特約の内容に含まれている可能性があるため、契約時は詳細まで確認しましょう。
また、原状回復工事の業者を選ぶ際、次のケースに当てはまる場合は注意が必要です。
- 原状回復工事を行う業者が指定されている
- 安価な業者を選んだ
貸主が指定する業者でしか工事ができない場合、高い工事費用を請求される可能性があります。そのため、原状回復の「原状」とはどのような状態かを明確にするとともに、業者指定の有無についても確認しておきましょう。
とはいえ、原状回復費用を安く済ませるために安価な業者へ依頼すると、貸主が求める状態に戻らないこともあります。その場合、貸主自ら他業者に施工を依頼し、借主に請求するというトラブルに発展する可能性があるため、あまりにも安価な業者に依頼するのは避けるべきです。
契約前の物件状態を確認しておく
テナント物件にはスケルトンと居抜きの2種類があります。原状回復の要件を満たすためにも、契約前の物件の状態をよく確認しておきましょう。
スケルトン物件
スケルトンは「骨組み」を指す言葉です。そこから転じてスケルトン物件は、柱・床・壁・梁などの建物を支える基礎的な部分のみの状態を指します。
スケルトン物件の原状回復は、原則としてスケルトンの状態にして返却しますが、貸主や次の借主から同意が得られれば居抜きでの返却も可能です。
居抜き物件
前のテナントが使用していた設備や内装を、そのまま引き継ぐ形態を居抜き物件といいます。
居抜き物件の原状回復では、契約時に引き継いだ備品を返却する必要はありません。前のテナントの備品を譲り受けている(造作譲渡)状態であることから、退去する際は譲り受けた物すべてを撤去するのが一般的です。
そのため、あらかじめ貸主と原状回復における契約内容をよく確認しておき、想定外の出費が発生しないよう注意しましょう。
物件の用途を説明する
賃貸借契約を結ぶ際、貸主に対して物件の使用目的を説明する義務があります。説明した内容とは異なる目的で物件を使用した場合、用法遵守義務違反に該当します。
用途遵守義務違反になったからといって、即座に契約が解除されるわけではありません。ただし、その違反が原因で後日退去を申し渡されたり、貸主に損害を与えた場合は損害賠償を請求されたりするため、注意が必要です。
仮に業態を変更したい場合は、その旨を前もって貸主に相談しましょう。
敷金が返却されるか確認する
敷金は原則として、原状回復費用や未払賃料などを差し引いた金額が返却されます。
そのため、原状回復や滞納などによって大幅に減らされることもあります。場合によっては、返還されるどころか、追加で費用を請求されることも考えられます。
トラブルに発展しないためにも、どの程度の規模で原状回復を行い、敷金がいくら返却されるのかあらかじめ確認しておきましょう。
また、物件によっては特約に敷金償却(敷引き)が指定されているケースもあります。
敷金償却とは、退去時に返還されない敷金の割合を表した特約です。このような特約項目を見逃すと、退去時に返還される敷金が大幅に減額されることもあるため、十分に注意が必要です。
テナント契約におけるトラブル事例

ここまでにお伝えした注意点とあわせて、テナント契約のトラブル事例を理解しておくことも重要です。
さまざまなケースを想定しておくとトラブルに巻き込まれるリスクが減ります。
設備や造作の修理・修繕はどちらが行うのか
一般的にテナントの設備は貸主、造作(入居してから取り付けた物で取り外し可能な物)は借主がメンテナンスや修理を行います。
例えば、エアコンが入居前から取り付けてあった場合の修理・修繕は、どちらが行うのかでトラブルになるケースもあります。
エアコンが前の借主が残した残置物である場合は、借主が修理を行うのが原則です。一方、もともと備え付けられていた設備であれば、貸主が費用を負担し修理を行う必要があります。
エアコンに限らず、自動ドアや排気ダクトなどでも同様のトラブルが起こりやすいので要注意です。そのため、契約前に設備や残置物のメンテナンス・修理について話し合い、特約として追加してもらうことが大切です。
雨漏りによる損害はどちらに責任があるのか
雨漏りによって設備や什器が濡れてしまい、損害が発生した際に、オーナーが対応してくれない可能性があります。営業を中止せざるを得ない状況であったため、補償金を要求したものの、貸主が拒否することも考えられるでしょう。
本来であれば、雨漏りによる損害の補償は貸主が行う義務があります。しかし、拒否される場合や、対応が遅いケースも想定し得るのが現状です。
このようなトラブルでは、根気強く要求し続ける、または法的措置も検討しましょう。
テナント契約時のポイント
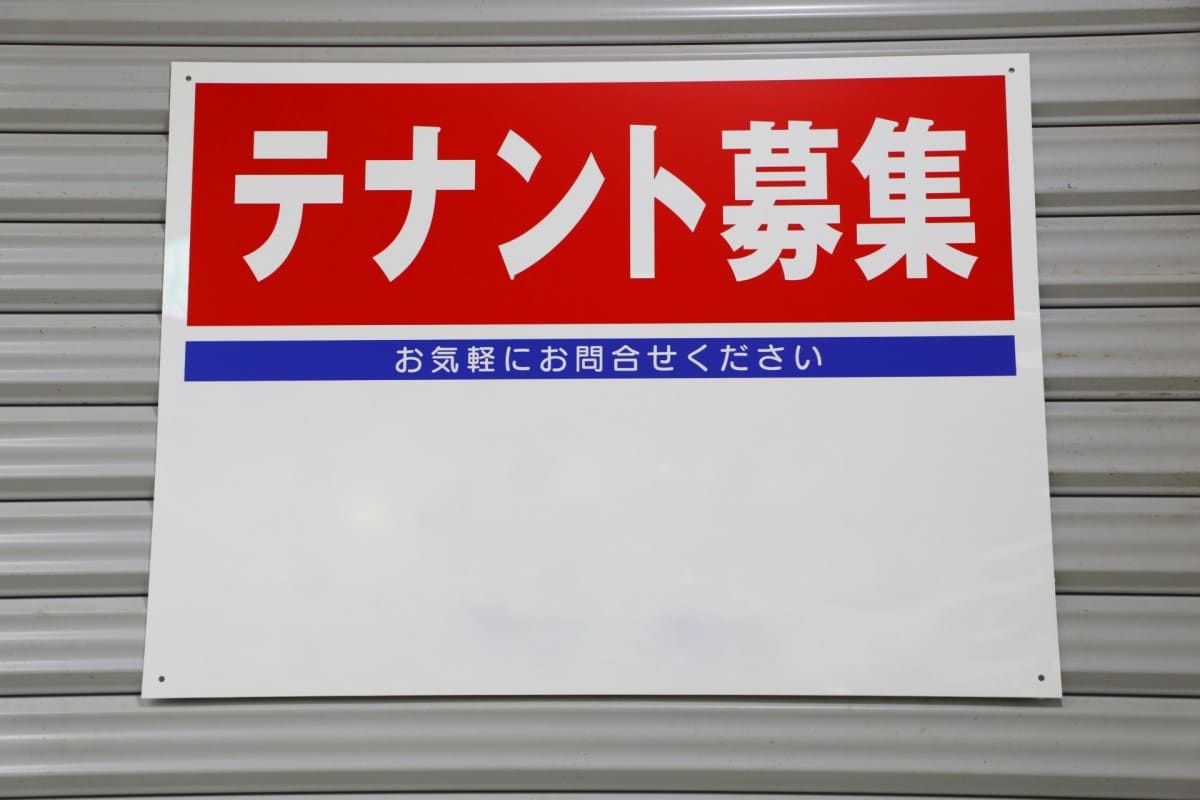
前述した注意点とともに、次のようなポイントを押さえておきましょう。事前にコンセプトや財務状況などを明確にすることで、テナント契約から開業へとよりスムーズに進められます。
- 店舗の形態やコンセプトを決める
- 財務状況や業務内容を明確にする
店舗の形態やコンセプトを決める
店舗ビジネスを始める段階で最も重要なのが物件選びです。
自社にとって適切な物件を見つけるには、商品・サービスの内容やターゲットユーザー、営業規模などの店舗コンセプトを明確にすることが重要です。
仮に家族連れがターゲットで、安心安全・健康をコンセプトとした飲食店の場合、新興住宅地や駅周辺のショッピングモールなどの立地が挙げられるでしょう。また、駐車場やテラス席を設置するなど、必要な要素を挙げていけば、自ずと必要な物件の条件も明確になります。
コンセプトを決める際は、次のような要素を検討しましょう。
- エリア・立地
- アクセス方法
- 路面店や空中店舗といった種別
- 周辺エリアにおける競合の有無
- テナント賃料
財務状況や業務内容を明確にする
テナントの入居審査を通過しやすくするには、次のポイントを押さえておきましょう。
- 財務状況が明確で安定した業績が見込める
- 企業の事業内容が明確である
- 本人と連帯保証人の身元が明確である
一方で、営業利益の見通しが賃料に見合わない、あるいは継続的な売上が見込めないようだと、審査が通りにくくなります。
そのため、貸主が客観的な数値で借主を評価できるよう、事業計画書や決算書を用意しておくと良いでしょう。ビジネスの実績がない方は、創業計画書や資金繰り計画書を用意し、細部まで詳細に記載することが重要です。
テナント契約時の注意点を押さえてトラブルを回避しよう

テナント契約時は、賃貸借契約書や原状回復の内容、物件の状態など、いくつか注意すべきポイントが存在します。
特に、契約書の特約や原状回復の詳細を把握していなかったことで、トラブルになるケースがあるため、十分に注意が必要です。トラブルを回避するためにも、本記事で紹介した注意点やトラブル事例を押さえ、テナント契約を進めていきましょう。
テナント物件をお探しの方へ
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。





 で
で