保証金は、賃貸物件を契約する際に借主から貸主に支払い、退去時に返ってくるお金です。
保証金とよく似た言葉として敷金がありますが、「保証金と敷金の違いがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、両者の違いを解説するとともに、テナント契約における保証金や敷金の注意点をお伝えします。さらに、退去時の保証金や敷金の返還額を減らさないためのポイントも解説しています。
これからテナント契約を予定している方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
保証金と敷金の用途は基本的に同じ
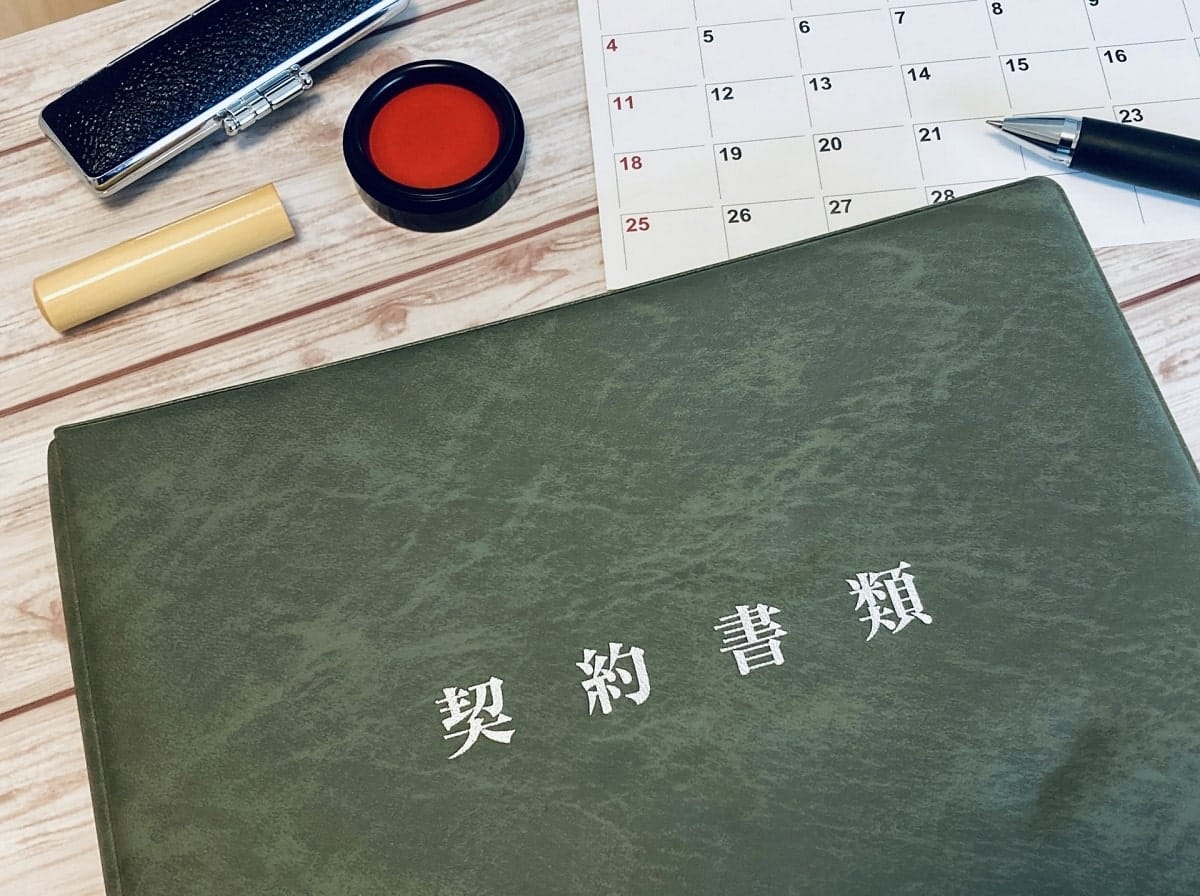
結論からいえば、保証金と敷金は基本的に同じ性質を持つものです。しかし実際には地域の慣習によって異なる部分もあるため、基本的な知識を理解しておきましょう。
どちらも契約時に貸主に預けるお金
一般的にテナント契約を結ぶ際は、借主から貸主に保証金もしくは敷金を支払います。
保証金や敷金は、物件を利用する期間中に発生するさまざまなリスクに備えるための費用です。
一般的に保証金や敷金は、退去時に発生するクリーニング代や修繕費といった費用に充てられます。そして、預けていた保証金や敷金からその費用が差し引かれ、退去時に残りの金額が返還される仕組みです。
2017年に民法が改正され、名目が保証金など別の名称であっても、実質的に債務担保を目的としたお金であれば敷金とみなされるようになりました。つまり、保証金と敷金は法的には同じ性質のものであるといえます。
保証金は主に関西に多い慣習
保証金という用語は、関西や九州などの西日本地域で敷金の代わりに使われるケースが多いようです。
ただし、不動産会社や物件によっては、保証金と敷金が同様に扱われるとは限りません。保証金と敷金で相場に大きな差が現れたり、そもそもの捉え方が異なったりする可能性もあるため、注意が必要です。
関西や九州では、「敷引き」と呼ばれる制度が残っている地域もあります。敷引きとは、敷金のうち退去時に返還されない部分を指します。金額は賃貸借契約書に明記されているため、契約時によく確認しましょう。
参考:アーバン企画開発グループ|アーバンレポート VOL.2019-8(第242号)
テナント物件の保証金や敷金にまつわる注意点

保証金や敷金について、「退去時に返ってくるお金」という理解だけでは不十分です。
経理処理や日々の店舗運営にもかかわる部分のため、こちらでお伝えする6つの注意点を正しく理解しておきましょう。
- 住居用の保証金や敷金に比べて相場は高め
- 保証金や敷金の一部が返還されない場合もある
- 返還の有無によって経理処理が異なる
- 家賃の滞納分は保証金・敷金で払えない
- 退去時はすぐに返還されるとは限らない
- 退去時に追加費用が必要になる可能性がある
住居用の保証金や敷金に比べて相場は高め
一般的な住居用物件の保証金や敷金は、家賃の1~2ヶ月分程度が相場です。一方、事業用物件の場合は家賃の10~12ヶ月分と、高めに設定される傾向があります。
このような違いが生まれる理由としては、退去時の原状回復費用が高額になりやすい点が考えられます。
例えば、借主が物件を利用して飲食店を開く場合、特に厨房周りでは、どうしても内装の汚れや設備のキズなどが発生してしまいがちです。住居用の物件に比べ、修繕しにくい汚れやキズが残ってしまう可能性が高いため、リスク回避のための保証金や敷金が高めに設定されています。
つまり、テナント物件を契約する際は、初期費用が高額になりやすい点に注意が必要です。
保証金や敷金の一部が返還されない場合もある
物件によっては、償却や敷引きによって、保証金や敷金の一部が返還されないケースもあります。
償却とは、預け入れた保証金が徐々に減っていく制度です。契約更新時に減額分を新たに請求されるケースもあります。
敷引きとは、契約段階で敷金の一部を返還しない旨、特約を付けておく制度です。
いずれも退去時の返還額が減少する制度ですが、原状回復費用に充当されるか否かという点に若干の違いがあります。一般的に敷引きのお金は原状回復費用に充てられますが、償却の場合は充当されません。
テナント契約時は、償却や敷引きの有無、返還条件をよく確認しておきましょう。
返還の有無によって経理処理が異なる
物件の退去時における保証金や敷金の返還は、経理処理においても大きな影響を与えます。住居用物件と事業用物件では税務上の取り扱いが異なる部分もあるため、注意が必要です。
住居用物件の場合、保証金や敷金には消費税が発生しません。
一方の事業用物件では、返還される保証金や敷金は非課税、返還されないものは課税対象です。例えば、100万円の敷金のうち、30万円が返還されない契約(敷引き)になっている場合、その30万円にのみ消費税が課されます。
経理処理を行う際には、契約書の内容を確認し、保証金や敷金の返還の有無や条件に応じて適切な対応を取る必要があります。判断に迷う場合は、税理士や近くの税務署に相談しましょう。
家賃の滞納分は保証金・敷金で払えない
保証金や敷金は、物件の修繕や退去時の原状回復工事に備えるためのお金です。
したがって、家賃を滞納したからといって、滞納分を保証金や敷金と相殺することは困難です。保証金や敷金の金額にかかわらず、借主は契約にもとづき家賃を遅滞なく支払う責任があります。
そのため、保証金や敷金を預けているからといって安堵せず、家賃を滞納しないよう、適正な資金計画を立てておくことが重要です。
参考:公益財団法人 不動産流通推進センター|賃借人は、入居中の滞納家賃を敷金と相殺するよう請求できるか
退去時はすぐに返還されるとは限らない
保証金や敷金の返還タイミングは、民法第622条の2で次のように規定されています。
- 契約終了後、借主が賃貸物を返還した際
- 借主が適法に賃借権を譲渡した際
そのため、保証金や敷金の返還を求めるには、物件の明け渡しや原状回復工事を完了させておく必要があります。無論、「保証金(敷金)を全額返還しなければ部屋を明け渡さない」といった主張は成り立ちません。
さらに、保証金や敷金の返還時期は契約条件によっても異なります。原状回復工事の期間によっては、返還が数ヶ月先になるケースもあります。その分、別のテナントに乗り換える際に、前テナントの返還金を資金に充てるのは難しいため、十分に注意が必要です。
契約前に返還条件をよく確認し、物件の明け渡しや原状回復工事がスムーズに進むよう、綿密な計画を立てておきましょう。
退去時に追加費用が必要になる可能性がある
物件を退去する際、原状回復費用が保証金や敷金から差し引かれて返還されますが、予期せぬ追加費用が発生するケースも考慮しなければなりません。
原状回復費用が予想以上に高くなり、保証金や敷金だけではまかなえない場合、追加費用を支払うよう求められる場合があります。
このような事態に備えて、契約時にどの程度の原状回復工事が必要なのかを明らかにし、契約書に記載しておきましょう。
また、見積金額や工事内容に納得できない場合は、複数の施工会社に相見積もりを依頼する、見積内容を細かく確認して相場を調査するなどの対策が考えられます。
保証金や敷金の返還額を減らさないためのポイント

保証金や敷金は退去時に全額が返ってくるとは限りませんが、できるだけ返還額を多く残すための工夫も大切です。
そのためには以下のポイントを押さえておきましょう。
- 契約内容をしっかりと確認する
- 契約時の物件の状態を記録しておく
- 汚れや破損を防ぎ原状回復費用を抑える
- 居抜き物件として譲渡できないか交渉する
契約内容をしっかりと確認する
物件を退去する際に保証金や敷金の返還額を減らさないためには、契約書をしっかりと読み、償却・敷引きの基準や原状回復の範囲を理解しておきましょう。
退去時に発生する費用を事前に見積もっておけば、予想外の支出を避けられます。特に、原状回復にかかる費用やクリーニング料など、契約にもとづいて差し引かれる項目を事前に把握しておくと、トラブルを未然に防げます。
契約内容には特約事項も含まれる場合があるので、十分に確認しましょう。特に、保証金や敷金の返還に関しては、償却や敷引きについて言及されている可能性があります。
契約書には複雑な記述も多く含まれますが、トラブルを避けるには細部まで目を通し、内容を理解しなければなりません。必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、納得のいく契約を結びましょう。
契約時の物件の状態を記録しておく
入居時からすでに存在していたキズや汚れに関しては、原則として借主が原状回復費用を負担する必要はありません。しかし、これを主張するためには、入居時の物件の状態を明確に証明する必要があります。
物件を退去する際に保証金や敷金の返還をスムーズに進めるためには、契約時に物件の状態を正確に記録しておきましょう。
入居時には、物件全体や細部の写真を撮るなどして視覚的に証拠を残すのが効果的です。
契約書にも物件の状態に関する詳細を明記しておくと良いでしょう。具体的なキズや汚れ、損傷箇所などを契約書に詳しく記載しておけば、入居時からの変化や既存の損傷に対する責任を明確にし、将来的なトラブルを回避できます。
汚れや破損を防ぎ原状回復費用を抑える
事業用物件は不特定多数の人が出入りするため、住居用物件に比べて汚れや破損のリスクが高まります。退去時に汚れ・破損箇所が目立つと、原状回復費用が高額になり、保証金や敷金の返還額が減ってしまいます。
そこで、こまめなケアと計画的なメンテナンスによって、なるべく内装を綺麗な状態に保つことが大切です。
特に、油汚れやカビなどの問題が発生した際には、速やかに対処しましょう。こまめな清掃がされていれば、退去時における清掃作業が簡略化され、クリーニング代を抑えられます。
物件内の状態を定期的に点検し、問題を発見した場合は早急に対応することで、退去時のトラブルを未然に防げます。
居抜き物件として譲渡できないか交渉する
店舗経営者が原状回復費用を抑え、保証金や敷金の返還額を最大化する方法として、居抜き物件の契約を検討するのも一案です。
居抜き物件とは、前の借主が使用していた内装や設備がそのまま残された物件のことです。
次の借主へと居抜き物件として譲渡できれば、内装や設備を既存状態で利用してもらえるため、原状回復工事にかかる費用を抑えられる可能性があります。結果的に、保証金や敷金の返還額が増えるでしょう。
居抜き物件は次の借主から見ても、いちから内装工事を行う必要がなく、開店資金を抑えられるという魅力があります。そのため一定の需要があり、できるだけ空室期間を短くしたい貸主にとってもメリットが大きいといえるでしょう。
必ずしも要求が通るとは限りませんが、双方の利益になるという意味では交渉してみる価値はありそうです。
居抜き物件の特徴については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:居抜き物件とは?スケルトンとの違いや契約の流れを解説
保証金や敷金の仕組みを理解してテナント出店を成功させよう

本記事では、保証金と敷金の違いに焦点を当て、テナント物件を退去する際に知っておくべき基礎知識についてお伝えしました。保証金と敷金は契約時に預け入れ、退去時に一部が返還される制度であり、どちらも基本的な用途は同じです。しかし、地域や契約条件によっては異なる慣習や注意点が存在します。
保証金や敷金の返還に関するトラブルを避けるためには、契約時にしっかりと条件を確認し、物件の状態を記録しておくことが不可欠です。また、物件の清掃や修繕に配慮することも返還額を増やす手段となります。
保証金や敷金の正しい知識を身に付け、スムーズにテナント出店のスタートを切りましょう。
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。





 で
で