狭いスペースでも営業ができ、コストを抑えられるスタンディングバーは、飲食店営業の初心者にとって魅力的な選択肢です。
しかし、「開業に向けて具体的に何をしたら良いかわからない」「どのような物件を選べば良いかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、スタンディングバーの特徴や魅力を詳しく解説するとともに、開業するまでの手順や、理想的な物件の選び方についても紹介します。
これからスタンディングバーの開業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
スタンディングバーとは

スタンディングバーとは、いわゆる立ち飲み形式のバーを指します。
一般的なバーに比べて手ごろな価格帯で、一人でも気軽に立ち寄ってお酒を楽しめるのが特徴です。また、椅子のあるバーに比べて席の移動が気軽にでき、初対面でも隣同士で会話が生まれやすいのも魅力の一つです。
スタンディングバーは、新たな出会いや交流が生まれる場所としても注目を集めています。
スタンディングバーを開業するメリット

気軽に立ち寄ってお酒を楽しめるのが魅力のスタンディングバーですが、開業においては次のようなメリットがあります。
- 初期費用が安く抑えられる
- 高い回転率が期待できる
- 固定客をつかみやすい
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
初期費用が安く抑えられる
スタンディングバーは比較的狭いスペースでも営業が可能なため、コストを安く抑えられるのがメリットです。
スタンディングバーでは一般的に、椅子やテーブルを設置せず、カウンターのみのスタイルを採用しています。これにより、内装がシンプルで済むため、初期費用を抑えられるのです。
また、狭いスペースであれば限られたスタッフの数でも効率的に営業できるため、人件費も抑えられます。
高い回転率が期待できる
通常の居酒屋や椅子のあるバーとは異なり、気軽にふらりと立ち寄りやすいスタンディングバーは、顧客の滞在時間が短くなりやすい傾向です。
そのため回転率が高く、狭い店舗でも多くの顧客を受け入れられます。結果として、効率的に売上を上げられるため、飲食店経営の初心者にとっても始めやすいビジネスモデルです。
さらに、滞在時間が短いと飲酒量も少なくなり、泥酔するまで飲酒する顧客が少ないというメリットもあります。
「仕事帰りに一杯だけ」といった形で立ち寄る一人客も存在するため、泥酔した顧客の対応や顧客同士のトラブルなどの心配は少ないでしょう。
固定客をつかみやすい
スタンディングバーは狭いスペースでも営業できるため、スタッフと顧客の距離が近い傾向にあります。そのため、話が弾んで仲良くなり、常連客となりやすいのが魅力です。
また、スタンディングバーは一人客を取り込みやすいという特徴もあります。
一般的な居酒屋は団体客を想定して、カウンターがなくテーブル席のみの店舗も多いため、一人客が訪れにくいケースがあります。
一方でスタンディングバーは一人でも立ち寄りやすく、ほかの常連客と交流したり、一人でゆっくり過ごしたりと好みに合わせた使い方ができるため、居酒屋が取りこぼした顧客を獲得しやすいでしょう。
スタンディングバーを開業するまでの6ステップ

スタンディングバーを開業するメリットがわかったところで、開業までにやるべきことを6つのステップに分けて見てみましょう。
- 店舗のコンセプトを決める
- 必要な資格や許可を取得する
- 物件を選ぶ
- 内装やデザインを決める
- 仕入先を検討する
- オープン日を決めて告知を行う
開業までにはさまざまな工程があります。余裕を持ってスケジュールを設定し、計画的に準備を進めましょう。
店舗のコンセプトを決める
一括りにスタンディングバーといっても、その雰囲気やターゲットとする顧客層は店舗によって異なります。最初にどのような店舗に仕上げたいのかを考え、具体的なコンセプトやターゲット層を設定しましょう。
コンセプトやターゲットは、物件選びや内装の選定における判断軸となります。「ビジネスパーソンが仕事帰りにふらりと立ち寄れるカジュアルなバー」「20代のカップルがデートで訪れる洗練されたバー」など、できるだけ具体的に考えておきましょう。
また、コンセプトは店舗の立地選びにも影響します。一般的に若者向けなら繁華街が、ビジネスパーソン向けならオフィス街が適しています。
集客に最適な立地を選ぶためにも、コンセプトをしっかりと決めることが成功の第一歩です。
必要な資格や許可を取得する
バーを開業するうえで必要な資格や営業許可がいくつかあります。なかには取得までに日数がかかるものもあるので、早い段階で準備を進めておきましょう。
- 食品衛生責任者:
食品衛生協会が開催する講習を受講すれば取得できる。調理師や栄養士といった特定の資格保有者は講習が免除される。 - 防火管理者:
従業員を含めた収容人数が30人以上の店舗であれば必要。講習を受講し、所管の消防署に届出書を提出する。 - 飲食店営業許可:
食品衛生責任者を指定し、申請書と添付書類を所管の保健所に提出する。申請から取得まで数週間かかる場合もあるため、スケジュールに余裕を持って申請しておく。 - 深夜酒類提供飲食店営業開始届出:
0時以降に営業する場合は必要。所管の警察署に届出書を提出する。営業開始日の10日前までに届出が必要。 - 特定遊興飲食店営業許可:
ダーツやカラオケなどの設備を設ける場合は必要。所管の警察署に許可申請書を提出する。判断に迷う場合は警察署で相談する。
物件を選ぶ
スタンディングバーの開業で、最も重要なポイントといえるのが物件選びです。
夜間に営業するスタンディングバーは、周辺の人通りや店舗の視認性が集客力に直結します。まずは不動産情報サイトなどで情報収集し、気になる物件が絞り込めてきたら、現地を訪れて確認しましょう。
物件選びで特に注意したいのが用途地域です。
地域の安全を保つため、各都道府県では商業地域や住居地域といった用途地域を設定しています。エリアによっては、特定の営業形態が制限されている場合があるため、立地を選ぶ際には注意が必要です。
用途地域は各自治体の窓口やホームページで調べられます。
内装やデザインを決める
スタンディングバーの内装やデザインは、店舗の雰囲気を大きく左右する重要な要素です。最初に決めたコンセプトを基準に厨房機器や店舗家具を選定し、「また来たい」と思ってもらえる快適な空間を作り上げましょう。
内装やデザインを決める際は、イメージの考案から施工会社の比較、機器や家具の選定まで多くの工程が必要です。準備期間に余裕を持ってスケジュールを立て、各工程を確実に進めましょう。
内装に特別なこだわりがなく、できるだけ費用を抑えたい場合は、居抜き物件を選ぶのも一案です。居抜き物件はすでに内装や厨房設備が整っているため、リフォームにかかる費用を削減できます。
居抜き物件については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:居抜き物件とは?スケルトンとの違いや契約の流れを解説
仕入先を検討する
知り合いや同業者の紹介を受けるか、酒販会社の試飲会に参加するなどして仕入先を検討し、品質の高いお酒を安く仕入れられるルートを見つけましょう。
仕入先との信頼関係を築ければ、より良い条件で取引でき、コストの削減にもつながります。また、地域の情報や最新のトレンドなど、スムーズな情報収集につながるのも利点です。流行りのお酒や季節に合ったメニューを提供することで、顧客に新しい楽しみを提供できます。
仕入れについてはお酒だけでなく、おしぼりや割り箸などの消耗品も考慮する必要があります。これらの品も卸売会社などからまとめて仕入れ、効率的かつコストを抑えながら質の高いサービスを提供できるよう心がけましょう。
オープン日を決めて告知を行う
準備が整ってオープン日を決めたら、積極的に告知を行いましょう。Web広告や折り込みチラシなどのさまざまな手段を組み合わせ、開店した事実を広範囲に宣伝します。
告知にかけられる予算が限られている場合は、補助金制度を利用するのも一つの手段です。
例えば、小規模事業者持続化補助金は、販路開拓などの取り組みを支援する制度で、チラシの作成や看板の設置といった広告宣伝費も補助の対象となります。
ただし、補助金の申請には手間と時間がかかるため、補助を受けられる金額とのバランスを考え、メリットが大きいようであれば利用すると良いでしょう。
なお、集客アイデアについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:飲食店の集客アイデア11選!すぐに実践できる方法をまとめて解説
参考:小規模事業者持続化補助金
スタンディングバーの物件選びのポイント

スタンディングバーの開業で最も重要なのは物件選びです。
以下のポイントを押さえて条件に合う物件を見つけ出し、理想の店舗を構築しましょう。
- 立地と店舗のコンセプトが一致している
- 外から店内の様子がよく見える
- スペースが広すぎず狭すぎない
立地と店舗のコンセプトが一致している
物件選びにおいては、店舗のコンセプトと立地が一致していることが最大の鍵です。
例えば、気軽に入店できるカジュアルな雰囲気を目指す場合は、繁華街や娯楽施設の近くなど、利便性が高く人通りの多い場所が適しています。
一方、静かで落ち着いた雰囲気の店舗であれば、路地裏やビルの地下などを選ぶことで、隠れ家のような空間を演出できます。
また、ターゲットとなる客層がよく訪れる場所を選ぶことも大切です。仮にビジネスパーソン向けのスタンディングバーであれば、繁華街よりもオフィス街の近くが適しています。
交通アクセスの良さや利便性も大切ですが、店舗のコンセプトとのバランスも考えながら立地を選びましょう。
外から店内の様子がよく見える
店舗のコンセプトにもよりますが、基本的にスタンディングバーは予約をせずふらりと立ち寄れるため、外から店内の雰囲気がよく見える構造がおすすめです。
外から店内が見えると、店舗の雰囲気やにぎわいが通行人にも伝わり、初めて訪れる客や一人客を呼び込みやすくなります。
外観やディスプレイにも工夫を重ね、つい気になって足を運びたくなる魅力的な雰囲気に仕上げましょう。
スペースが広すぎず狭すぎない
立地や外観と同様、スペースへの配慮も物件選びの重要なポイントです。
狭いスペースでも営業できるのがスタンディングバーの魅力ですが、あまりにも狭いと動線の自由度が下がります。スタッフの動きが制限されるとドリンクや料理の提供が滞り、顧客満足度が低下するかもしれません。
かといって広すぎても移動距離が長くなる分、効率的な運営が難しくなります。店舗全体に目が届き、必要最小限の動きで接客できる程度の広さが理想的といえるでしょう。
物件選びにおいては、快適な動線やスタッフの効率を考慮し、広さと狭さのバランスを見極めることが重要です。
ポイントを押さえてスタンディングバーの開業を成功させよう

限られたスペースと人数でも営業できるスタンディングバーは、飲食店経営の初心者でも始めやすい店舗形態です。一般的に顧客の滞在時間が短いことから回転率が高く、効率的に売上を上げられるのも大きな魅力といえます。
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。

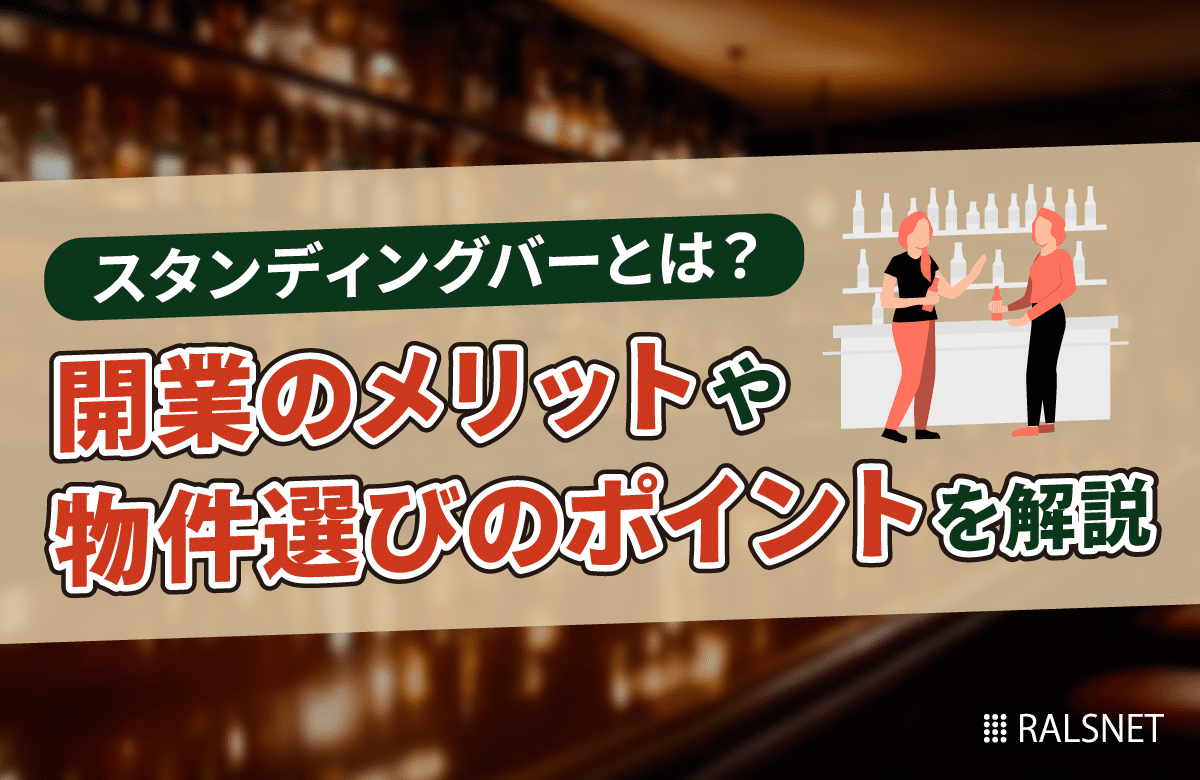



 で
で