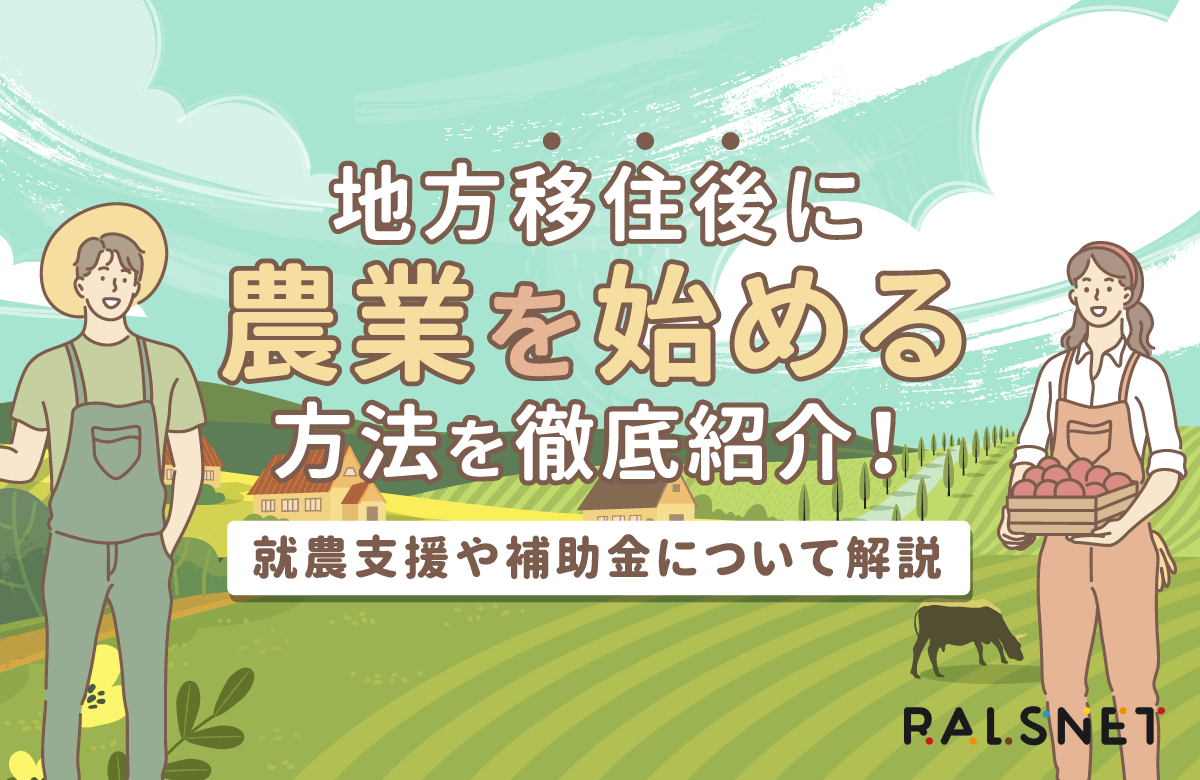地方への移住を機に、都会ではできなかったことにチャレンジしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
なかでも農業は、田舎の自然とスローライフを体験するにはぴったりな方法といえます。
しかし、いきなり農業を始めるのは、ハードルが高いと感じるはずです。
そこで本記事では、移住先で農業を始める方法に加え、移住や就農などに役立つ支援・補助金制度について解説します。
目次
まずは移住後にどのような農業を始めるかを決めよう

農業には、規模の大きさや事業内容によって、いくつかのスタイルがあります。そこで、農業を始めるにあたって、どのようなスタイルにするのかを考えましょう。
例えば、自宅の庭で農作物を育てる家庭菜園や、本業を持ちながら副業として農業に従事する方法などがあります。
ここでは複数の農業スタイルについて取り上げていますので、自身と相性が良いものを見つけてみてください。
趣味として農業に取り組むなら家庭菜園
家庭菜園は、農地ではない場所で手軽に野菜や果物を栽培する方法です。自宅の庭やベランダなどで作物を作れるため、簡単に始められるのが魅力です。
基本的には自宅で食べる分のみを生産するため、副業などの収益にはなりにくいですが、趣味として容易に始められます。
地方移住を機に、新しい趣味を手にしたいという方におすすめです。
別の仕事をしながら農業に従事する
農業を始める場合には、現在の仕事を続けながら農業を始める方法もあります。
具体的には、以下のような方法が代表的です。
- 週末農業
- 兼業農家
週末農業
週末農業は、平日は会社などで働きながら、休日のみ農業に取り組むスタイルです。
本業で収入を得ながら、市民農園やレンタル農園などで農業に挑戦できます。
収入減を確保しながら農業に従事できるため、本格的な農業を始める前のお試しにもおすすめです。
兼業農家
兼業農家は、別の仕事をしながら農業に従事するスタイルです。
農業収入をメインとする第一種兼業農家と、農業以外の収入をメインとする第二種兼業農家に分けられます。そのうち、第二種兼業農家は、週末農業と同じく本業の収入を得ながら農業に挑戦できます。
空いた時間を使いながら、農業で副収入を得ることも可能です。
仕事として農業に従事する
地方移住を機に本格的に農業を始め、メイン収入を確保する方法もあります。自分で農地を用意する場合や、すでに農業を営んでいる人のもとで働く場合など、状況に応じて選択しましょう。
具体的なスタイルとしては、以下のような種類が代表的です。
- 半農半X
- 農業バイト・パート
- 農園継承
半農半X
半農半Xは農業スタイルの一つで、農業とほかの仕事を組み合わせた働き方です。
「X」の部分には、自分の好きな仕事を当てはめます。
例えば、農業を行いながら民宿を運営し、自分の理想的なライフスタイルを実現したい場合は、「半農半民宿」となります。農業でも収入は得るものの、あくまで半分の労力に抑え、残りの半分を自分の好きな仕事に打ち込むという考え方です。
農業バイト・パート
自分で農業を始めるのではなく、第三者の農家や農園で給与を得ながら働くことも検討できます。
すでに知識やノウハウを持った人のもとで働けるため、将来的に独立をしたい方におすすめです。
農園継承
農園継承は、実家や親族等から農地を引き継ぐ方法です。
すでに土地や環境が整っている状態から始められるため、いちから農業を始めるよりも難易度が低い点がポイントです。
また、最近では、農園継承を考えている方向けのマッチングサービスも登場し、引き継ぎや後継者探しの手間を随分と抑えられます。「他者から農園を引き継ぎたいものの、その相手が見つからない」という方にもおすすめのサービスです。
新しく自分で農業を始める
農業を始める際は、農地や設備を購入して新規で農業をスタートする方法もあります。
育てたい作物や就業スケジュールを自分で決められることから、自由度の高い働き方が実現できます。
また、新規就農者として認定を受けることで、農業者年金の一部補助や、農業経営基盤強化準備金制度を利用した税制面での優遇措置を受けられるのも特徴です。
ただし、土地や設備の購入費が高額になりやすい、作物が収穫できるようになるまでは収入が得られないなど、参入の難易度が高いといえます。また、収入を農業に頼ることになるため、リスクがあることにも注意が必要です。
新規就農支援や農業研修など、自治体の支援制度を有効活用し、安定した収入を得られるようにしましょう。慣れないうちはアルバイトやパートに従事し、まずノウハウを獲得することから始めるのも大切です。
移住後に農業を始める流れ

移住後に農業を始める際の手順は次の通りです。
- どのような農業を始めるかを考える
- 農業に関する情報収集をする
- 住みたいエリアを考える
- 農業体験やインターンシップに参加する
それぞれの手順について、詳しく解説します。
1. どのような農業を始めるかを考える
先ほど紹介したように、まずはどのような農業スタイルを採用するかを検討しましょう。
スタイルによって、農業を始めるための準備期間や難易度が大きく変わります。また、収入を得る方法や生活スタイルにも大きく影響します。
特に、移住後の農業を考えている方は、移住先の検討や暮らしに関する情報収集も入念に行っておきましょう。
2. 農業に関する情報収集をする
農業には知識やノウハウが必要になるため、徹底した情報収集が欠かせません。
全国農業会議所が運営している「農業をはじめる.JP」や、農林水産省が発行している「新・農業人ハンドブック」には、新規就農者に向けた情報が数多く掲載されています。
また、農業を始める方向けのセミナーに参加するのもおすすめです。
3. 住みたいエリアを考える
農業を始めるための準備ができたら、具体的な移住先を検討します。
住む場所や遊休農地を探す際は、自身の農業スタイルに合わせて選り分けると良いでしょう。また、地域によって育成できる農作物も変わるため、地域ごとに得意とする生産物を調べることも重要です。
JAグループは地域ごとに新規就農支援を行っているため、地域選びの参考にしてみてください。
4. 農業体験やインターンシップに参加する
実際に農業に取り組む前に、農業体験やインターンシップに参加することも大切です。
事前に調べた情報を肌身で体験でき、より実践的な知識を身につけられます。
農業体験やインターンシップでは、主に作物の種付けから収穫までを体験できます。農業の現場を実際に体験することで、移住後の就農をスムーズに行える点がメリットです。
農林水産省やJAのホームページでは、農業体験やインターンシップの募集を随時実施しています。移住を検討している地域の募集がないかもチェックしてみましょう。
移住後に農業を始める際に利用できる補助金

ここからは、移住後に農業を始める際に利用できる補助金の概要や特徴について解説します。
新規就農者に向けた補助金としては、以下のようなものがあります。
- 強い農業づくり総合支援交付金
- 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
- 青年等就農資金
- 農業近代化資金
強い農業づくり総合支援交付金
強い農業づくり総合支援交付金は、国内の農畜産物を安定供給するために、農林水産省が提供している補助金制度です。
支援金には以下の4つのタイプがあり、生産規模や農業スタイルに応じて補助金を受け取れます。
- 産地基幹施設等支援:
農業に必要な集出荷施設など、産地の基幹施設の整備を支援する制度。投資額の1/2以内の支援金が受け取れる。 - 卸売市場等支援:
卸売市場施設や共同物流拠点施設などの整備に活用できる支援金。補助率は費用の4/10以内。 - 先駆的モデル支援:
農産物の安定した生産・供給のための先駆的なモデルを支援。推進事業の場合は最大5,000万円、整備事業の場合は最大20億円(いずれも1/2の補助率)が受け取れる。 - 農業支援サービス事業支援:
農業用機械の購入に利用できる支援制度。補助率は1/2以内で、最大1,500万円の支援が受けられる。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は農林水産省ホームページ|強い農業づくりの支援をご確認ください。
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)は、農業の新しい担い手を支援するために、農林水産省が提供している支援金です。
支援の内容としては、就農前の研修を後押しするための資金と、就農直後の経営を支援する資金が交付されます。
就農準備資金では、都道府県認定の農業大学校などで研修を受ける就農希望者に、年間最大150万円を支給しています。支給期間は最長2年間です。
経営開始資金は、農業経営スタートから経営安定化までの最長3年間のみ、年間最大150万円を支給する制度です。
農林水産省では新規就農者育成総合対策として、補助金以外に農場の機械・施設の導入支援や社会人向け研修などを実施しています。特に本格的な農業を始めたい方は、あわせて制度を活用してみてください。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は農林水産省ホームページ|就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)をご確認ください。
青年等就農資金
青年等就農資金は、日本政策金融公庫が行う新規就農者向けの支援制度です。新たに農業経営を始める方に対して、無利子の資金を融資しています。
農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や、販売施設の購入費を対象に、最大で3,700万円の融資が受けられます。返済期間は据え置き期間を含めた17年以内です。
資金を受け取るためには、経営改善資金計画を作成し、特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。
総返済額を抑えたうえで、機械の購入費や果樹の育成費などの融資を受けたい方におすすめです。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は日本政策金融公庫ホームページ|青年等就農資金をご確認ください。
農業近代化資金
農業近代化資金は、全国の金融機関やJAバンクなどが提供している低金利の融資制度です。新規就農に必要な資金の一部を、借り入れという形で支援してもらえます。
実際に借り入れできるのは、施設の改良や造成、果樹や家畜の育成、事業の持続などに必要な資金です。
借入限度額は、個人の場合は1,800万円、法人や団体は2億円です。金利は1.30%ですが、認定農業者の場合は借入期間に応じて0.65~1.15%の金利が適用されます。
※2024年12月に執筆した記事です。最新情報は農林水産省ホームページ|農業近代化資金をご確認ください。
北海道に移住して農業を行うメリット

新規就農を目指す方の移住先には、広大な大地が広がる北海道がおすすめです。
次の通り、北海道に移住し農業を始めると、さまざまな恩恵を受けられます。
- 土地が安く初期投資額が低く抑えられる
- 多くの農家が開業していて雇用就農がしやすい
- 幅広い作物を育てやすい
- 北海道というブランドが手に入る
土地が安く初期投資額が低く抑えられる
広大な大地を持つ北海道は、地価の低い地域が多いことから、土地の購入代金を抑えられます。
初期投資額が高額となり、新たに農業を始めるのに躊躇していた方にとっては、大きなメリットです。
国土交通省が公表している公示地価を見ると、北海道のなかには1平方メートルあたり数千円程度の地域も数多く存在します。
多くの農家が開業していて雇用就農がしやすい
114万ヘクタール以上の耕地面積を持つ北海道では、多くの人が農業に従事しています。
農家戸数は3万2,300戸と全国比3.5%程度ですが、そのうちの約74%は農業を主な収入としていて、農業が盛んに行われていることがわかります。
そのため、自分で農地を持たずに、既存の農家への就業を検討している方におすすめです。
雇用就農でさまざまなノウハウを取得しておくと、本格的な農業を始める際に役立ちます。
幅広い作物を育てやすい
地域によってさまざま地形や気候を持つ北海道は、地域ごとに異なる作物が栽培されていることも特徴です。
道北や道東には、オホーツク地方や十勝地方という広大な農地が広がっており、大規模な酪農や畑作が行われています。
道南は、北海道のなかでも温暖な気候に特徴があり、主にお米や野菜が収穫されています。豆類や馬鈴しょなどの畑作物をメインに、集約的な農業を実施しているケースも少なくありません。
育成・収穫したい農作物によって地域を選べることから、選択肢の幅を広げられます。
北海道というブランドが手に入る
北海道で農業を行うメリットとして、生産品のブランド価値がつくメリットもあります。
都道府県の魅力度ランキングを提供するブランド総合研究所が実施した、「食事がおいしい都道府県ランキング」において、北海道は全国で1位を獲得(2023年時点)しており、食材のブランド力が伺えます。
北海道産というブランド力をつけて農産品を全国的に販売できるのは、本格的な農地経営を行いたい方にとっては大きな強みです。
家庭菜園や就農には農業王国の北海道がおすすめ

今回は、地方移住で農業を始める方法や、農業を始める支援・補助金制度について解説しました。
農業を始めたいと考えている方にとって、地方への移住はまたとない機会です。理想のライフスタイルを手に入れるために、自分にあった地域への移住を目指しましょう。
本記事でも紹介した通り、北海道は農業に適した地域といえます。
以下の記事では、北海道に移住するメリットを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。