焼肉屋の開業は、ほかの飲食店に比べて多額の資金が必要です。また、メイン商品である肉の仕入れや、物件選びに資格取得など、準備すべきことは尽きません。
そこで本記事では、焼肉屋を開業する際に知っておきたい情報や、必要な知識を学ぶ方法について解説しました。
焼肉屋を開業するメリット・デメリットのほか、記事の後半では「実際に儲かるのか?」「廃業率はどのくらいなのか?」といった疑問にもお答えしますので、参考になれば幸いです。
目次
焼肉屋の開業費用

焼肉屋の開業にかかる費用としては、以下の2種類があります。
- 初期費用:1,500万円以上
- 運転資金:月300万円以上
それぞれの内訳や費用を詳しくみていきましょう。
初期費用
焼肉屋を開業する際の初期費用は、1,500〜3,000万円は用意しておくと安心です。小さめの店舗でも、1,000万円以上は必要です。
焼肉屋の内装工事費用は高額であり、数ある飲食店のなかでも特に資金がかかります。
以下の表に、焼肉屋を開業する際の初期費用をまとめました。
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 物件の取得 | 300~500万円以上 |
| 内装工事 | 700~2,000万円以上 |
| 設備・備品 | 250~600万以上 |
| 仕入れ | 150万円 |
| 広告・宣伝 | 20~50万円 |
| 資格取得 | 3~6万円 |
| 合計 | 1,423~3,306万円 |
表内の金額はあくまで目安であり、工夫次第で安く抑えられる半面、こだわりや理想を追求するとより高額になることもあります。
なお、煙が発生する焼肉屋では、ダクトの設置は必須のため、空調設備工事は節約しにくいです。
運転資金
焼肉屋を開業するなら、運転資金は月に約300万円以上かかります。
運転資金とは、開業後に経営を続けていくうえで必要な資金です。物件の立地やスタッフの人数・食材の品質などによって大きく変動します。
以下の表に、焼肉屋を経営していくうえで必要な運転資金の目安をまとめました。
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 30~100万円 |
| 人件費 | 100~180万円以上 |
| 仕入れ | 150~300万以上 |
| 光熱費 | 10~20万円 |
| 広告宣伝費 | 0~30万円 |
| 合計 | 290~630万円 |
開業して間もなく軌道に乗るケースは少ないので、半年程度は利益無しで経営できるだけの資金が必要です。
とはいえ、自己資金で全額をまかなうのは難しい場合も多いでしょう。
次の項目では、焼肉屋を開業する際の資金調達について解説します。
焼肉屋を開業する際の資金調達方法

焼肉屋を開業する際の資金調達としては、以下の方法が挙げられます。
- 融資
- 助成金・補助金
- クラウドファンディング
- 友人・家族からの支援
上記の方法のなかでは、融資が資金調達のハードルがもっとも低い方法です。ただ、初めて開業する方は、金融機関の審査を通ることがやや難しいです。
しかし、日本政策金融公庫の融資制度は、初めて開業する方も審査が比較的通りやすいといわれます。担保や保証人が無くても制度を活用できるので、検討してみてはいかがでしょうか。
また、フランチャイズに加盟すると、本部が融資をサポートしてくれる場合があります。
いずれにせよ、せっかく開業した焼肉屋を早期にたたむ事態を避けるためには、開業資金や融資額はできるだけ抑え、運転資金に回すのがオススメです。
飲食店の資金調達方法や、助成金・補助金の探し方は、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:飲食店は開業資金ゼロでも始められる?8種類の資金調達方法を徹底解説
飲食店の開業時に使える助成金・補助金|見逃さないための調べ方
焼肉屋を開業する際に必要な資格・届出

焼肉屋を開業する際には、以下の資格や届出が必要です。
- 食品衛生責任者
- 飲食店営業許可
- 防火管理者
また、「家畜商免許」という資格もあります。家畜商免許はオーナーが取得する必要はありませんが、仕入れ先のスタッフが取得していなければなりません。
それぞれの資格や届出について、詳しくみていきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、飲食店の衛生管理を行うスタッフであり、店舗に1人以上の在籍が義務付けられています。
食品衛生責任者の資格は、オーナーが所持しているケースが多いです。
各都道府県で養成講座が実施されており、6時間程度の講習を受けると資格が取得できます。
なお、調理師や栄養士などの資格があれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になることが可能です。
東京都の場合は、運転免許証かマイナンバーカードがあれば、オンラインでも講習を受けられます。受講料は教材費込みで12,000円(税込)です。
参考:一般社団法人東京都食品衛生協会「eラーニング型養成講習会」
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、焼肉屋に限らず、すべての飲食店を営業する際に必要な届出です。
許可を取るための手続きは、以下の流れで行います。
- 事前相談
→物件の工事着工前に完成図面を保健所に提出する - 書類を提出
→工事完成の10日前くらいに提出する - 施設検査の打ち合わせ
- 施設検査
→オーナーが立ち会う - 許可書の交付
参考:東京都保健医療局「-食品関係営業許可申請の手引-」
なお、東京都中央区の場合は、新規の申請で18,300円の手数料がかかります(参考:東京都中央区「営業許可業種と申請手数料一覧」)。
飲食店営業許可の申請や届出は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」により、オンラインでも手続き可能です。
物件の工事が完了してから相談や検査を申し込むと、不備があった場合にやり直さなければいけません。不要な出費を防ぐために、必ず事前に相談しましょう。
防火管理者
防火管理者とは、火災による被害を防止するための資格です。
従業員を含め、30人以上の収容人数である飲食店では、防火管理者を置かなければなりません。
防火管理者には2種類あり、以下のような区分けがされています。
- 甲種防火管理者
→すべての防火対象物で管理者になれる - 乙種防火管理者
→比較的小規模な防火対象物で管理者になれる
(※管轄の消防署により異なる)
受講料は甲種8,000円、乙種7,000円です。
参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火管理講習」
番外編:家畜商免許
焼肉屋を開業するにあたって、家畜商免許は必須ではありません。しかし、仕入れ先の事業者は家畜商免許を持っている必要があります。
家畜商免許とは、牛や豚・馬などの家畜を取引する際に必要な知識を習得していると証明する資格です。
具体的には、以下の3点を修了する必要があります。
引用元:一般社団法人 日本家畜商協会「家畜商になるためには」
- 家畜の取引に関する法令(4時間)
- 家畜の品種及び特徴(4時間)
- 家畜の悪癖、機能障害及び疾病(6時間)
仕入れ先の事業者が家畜商免許を持っていれば、安心して良質な家畜を仕入れられます。
ここまで、焼肉屋の開業に必要な資格・届出を解説してきました。ただ、食材や調理の知識を体系立てて学ぶことも欠かせません。
そこで次の項目では、焼肉屋の開業に必要な知識を学ぶ方法について解説していきます。
焼肉屋の開業に必要な知識を学ぶ方法

焼肉屋の開業に必要な知識を学ぶ方法として、下記の3つが挙げられます。
- 他店で修行する
- 本やYouTubeを見る
- セミナーに参加する
それぞれ詳しくみていきましょう。
他店で修行する
焼肉屋を開業する前に必要な知識を学ぶには、「他店で修行する」という選択肢があります。修行によって、肉の切り方や焼き方のコツ、仕入れ先・品質の見極め方を学べます。
特に飲食店での勤務経験がない場合は、ぜひ修行を検討したいところです。
焼肉屋の開業では肉の仕入れが一番難しいですが、他店で修行すると、仕入れ先の伝手をつかめる可能性があります。また、個人経営やオープン間もないお店で働くと、コスト管理や集客など、幅広い経験を積みやすくなります。
修行先を検討する際は、人手不足の店舗をリサーチすると、雇ってもらえる確率が高いです。さらに、焼肉屋を運営している卸売業者もあるため、より食材の品質を見極める練習ができるかもしれません。
また、修行の期間はあらかじめ決めておくことが大切です。事前に区切りを決めておけば、より緊張感をもって修行に集中できるでしょう。
他店での修行は焼肉屋を開業する際に大いに役立つためオススメです。
本やYouTubeを見る
焼肉屋の開業に必要な知識を学ぶ方法として、本やYouTubeを活用するのは非常に有効です。まず、ほしい知識を明確にしてから本やYouTubeを見ると、効率よく情報を得られます。
オンライン書店で「焼肉 開業」や「飲食店 開業」と検索すると、参考になる書籍が見つかります。ただし、焼肉屋に特化した書籍は古いものが多いので、注意が必要です。
また、YouTubeでは、飲食店コンサルタントや焼肉屋のオーナーがさまざまな情報を配信しています。特に、注意点や仕入れ方法、開業費用について詳しく解説している動画が多いです。
YouTube動画を使って学習する際のメリット・デメリットは以下の通りです。
- メリット:無料でどこでも視聴できる
- デメリット:視聴回数を増やすためにトレンドが重視されるため、全体的な知識を把握しにくいケースがある
本やYouTubeを上手に活用すると、焼肉屋の開業に必要な知識を効率よく学べます。
セミナーに参加する
焼肉屋の開業に必要な知識を学ぶ際は、セミナーへの参加も効果的です。
セミナーでは、ビジネスモデルや販路拡大に関する情報を学べます。
オンラインで行われるセミナーも多く、移動時間がかからないのはメリットです。また、質問タイムが設けられているセミナーもあるため、その場で疑問点が解決できるでしょう。
セミナーに参加する際は、焼肉屋に限らず飲食店の開業に関するセミナーも探してみましょう。資金調達やSNSの活用方法など、役立つ知識を得られる可能性があります。
公的機関が行うセミナーは、「J-Net21」や「日本政策金融公庫」で検索できます。信頼性が高く、初めての方でも安心です。
一方で、信頼性が低いセミナーもあるため、「楽に稼げる」「確実に儲かる」などの言葉には注意が必要です。まずは、公的機関や大手企業が主催するセミナーから参加することをオススメします。
焼肉屋の開業時の仕入れ方法
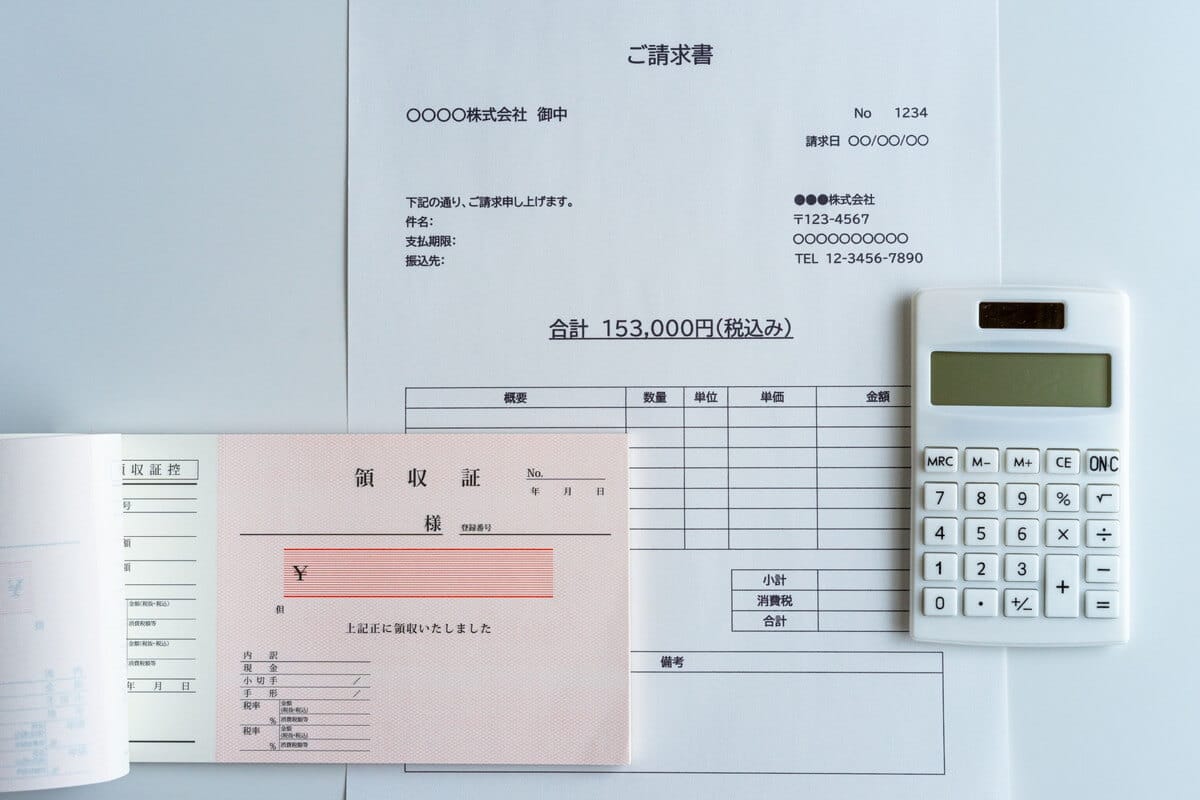
焼肉屋を開業するときに最も重要なステップは、食材の仕入れです。
卸売業者が市場で買い付けた肉を、焼肉屋が買い取るのが基本的な流れです。とはいえ、どのように卸売業者とコンタクトを取るべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。
食材を仕入れる際に、卸売業者とコンタクトを取るには、以下の2つの方法があります。
- インターネットで卸売業者を調べる
- 知人に卸売業者を紹介してもらう
それぞれ詳しくみていきましょう。
インターネットで卸売業者を調べる
焼肉屋の開業時の仕入れ方法として、インターネットを活用して肉の卸売業者を調べ、連絡を取る方法が挙げられます。
たとえば「食肉卸業者 〇〇(地名)」で検索すると、複数の情報がヒットしました。
多くの卸売業者は、電話やFAX・メールで問い合わせができるので、手軽に連絡を取れます。
ただし、卸売業者との取引は、信頼関係が重要です。付き合いが浅いと仕入れや少量の注文を断られることもあります。
信頼関係を構築するために、ある程度時間がかかることを理解しておきましょう。
また、大量に仕入れれば値引きしてくれる場合もあります。
知人に卸売業者を紹介してもらう
焼肉屋の開業時に食材を仕入れたい場合、知人に卸売業者を紹介してもらう選択肢もあります。飲食店経営者の知人がいるなら、そのネットワークを活用して信頼できる卸売業者を紹介してもらいましょう。
さらに、食材の展示会やイベントへの参加もオススメです。展示会やイベントで卸売業者と直接的な接点を持つと、信頼関係を築きやすくなります。「飲食店 展示会」「焼肉 展示会」などと検索すると、情報がヒットしやすいです。
焼肉屋を開業する形態

焼肉屋を開業する際には、以下の2つの形態が選べます。
- 個人でお店を開く
- フランチャイズに加盟してお店を開く
それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
個人でお店を開く
焼肉屋を開業する形態の一つに、個人でお店を開く方法があります。このスタイルでは、居抜き物件やスケルトン物件など、自分で店舗を借りて開業します。
関連記事:居抜き物件とは?スケルトンとの違いや契約の流れを解説
個人でお店を開く際は、仕入れ先の確保を自分で行わなければならず、軌道に乗るまでに時間がかかるケースも多いです。
また、開業手続きや設備の導入・スタッフの教育など、やるべきタスクが多くあります。
一方で、自分の理想に近いお店を自由に経営できる点は魅力的です。
「個人でお店を開く」方法は、自分のオリジナルなお店を持ちたいという強い思いがある人にオススメです。
フランチャイズに加盟してお店を開く
「個人でお店を開く」選択肢とはほかに、「フランチャイズに加盟してお店を開く」方法もあります。
フランチャイズとは、チェーン店の本部にお金を払い、ブランド名や既存の商品などを用いて経営する方法です。
この方法のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・開業してから軌道に乗るまでの時間を短縮できる ・ブランド名を使用できるので、集客の手間を軽減できる ・スタッフの手配・教育を支援している本部もある | ・フランチャイズの加盟料がかかる ・店舗づくりに制限がかかる ・経営の自由度が低い |
自由度が低くても効率的な経営をしたい人は、フランチャイズに加盟する方法をオススメします。
焼肉屋開業の準備をステップ別に解説

焼肉屋を開業する準備の流れについて、以下のステップ別にみていきましょう。
- 市場調査や競合調査を行う
- コンセプトやターゲットを決める
- メニュー・仕入れ先を決める
- 立地・物件を選ぶ
- 事業計画書を作成する
- 資金を調達する
- 資格取得の手続きを行う
- 人材採用・教育を行う
- 集客・宣伝を行う
市場調査や競合調査を行う
焼肉屋を開業する準備は、市場調査や競合調査から始めます。
まず、市場調査として、出店したいエリアの客層を調べましょう。ターゲットとする顧客層を明確にできます。
市場調査では、「地域の需要」「客層のライフスタイル」なども調べます。
次に競合調査として、他の焼肉屋がターゲットにしている客層も調査しましょう。
競合調査での主なチェックポイントは下記のとおりです。
- 繁盛しているお店はどんな店か?
- 内外装や接客の雰囲気はどうなっているか?
- メニューの方向性や価格帯は?
- 平日・週末の人の流れはどうなっているか?
また、市場調査や競合調査と並行して、自分の経験や強みを把握しましょう。自分の経験や強みが活かせる戦略を考えれば、独自性につながります。
市場調査や競合調査を通じて、自分の焼肉屋がどのように差別化できるか考えることが、成功への第一歩です。
コンセプトやターゲットを決める
市場調査や競合調査が完了したら、分析結果からコンセプト・ターゲットを決めていきます。コンセプト・ターゲットを明確にすれば、経営の方針が固まっていくでしょう。
焼肉屋のコンセプトの例としては、下記のような内容が挙げられます。
- おひとり様・2人客など少人数をターゲットにしたお店
- 家族で焼肉が楽しめるお店
- 贅沢にレアな部位を食べられるお店
- ヘルシーな赤身肉が食べられるお店
例えば家族連れをターゲットに設定するなら、価格帯は安めのほうが来店してもらいやすいです。ベビーカーも通りやすいように通路を広くしたり、子どもが持ちやすいように食器をプラスチック製にしたりといった工夫も考えられます。
このようにターゲットやコンセプトを設計すると、競合との差別化が可能です。
メニュー・仕入れ先を決める
コンセプト・ターゲット設定の次は、メニューや仕入れ先を決定します。
焼肉屋の開業には、魅力的なメニューと信頼できる仕入れ先を決めることが重要です。
まず、サイドメニューも含めて美味しいメニューを決めましょう。焼肉屋は原価率が高いため、サイドメニューで全体的なコストを下げるのが効果的です。例えば、キムチやチヂミ・ビビンバ・冷麺などのサイドメニューも人気です。
次に、良い肉の見分け方を身に着けておく必要があります。具体的には以下の点に注意しましょう。
- きれいで明るい赤色であること
- 水気が出ていないこと
- 適度なハリがあること
最後に、信頼できる仕入れ先を見つけます。仕入れ先の見つけ方は前述の「焼肉屋の開業時の仕入れ方法」で解説していますので、あわせてご覧ください。
立地・物件を選ぶ
前述の「コンセプトやターゲットを決める」ステップと並行して、立地・物件も選びましょう。ターゲットと立地は関連性が強いため、方向性にずれが生じると経営失敗につながりかねません。
駅チカや繁華街周辺で集客しやすい一等地は、すでに埋まっていることが多いです。そのため、繁華街から少し遠い二等地や三等地も検討する必要があります。
また、焼肉屋の居抜き物件を活用すれば、初期費用を大幅に抑えられます。
しかし、居抜き物件は「以前の店が閉店している物件」であるため、悪いイメージも引き継ぐリスクがあり、注意が必要です。
居抜き物件を探す際の注意点は、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:居抜き物件を探す際の注意点|よくある7つのトラブルをもとに解説
事業計画書を作成する
これまでのステップが完了したら、事業計画書を作成しましょう。
事業計画書とは、創業の目的や事業コンセプト・資金調達方法、事業の見通しなどを記載する計画書です。この書類は、融資や補助金を受ける際に必要となります。
形式に決められたものはありませんが、「日本政策金融公庫」や「J-net21」などでテンプレートを入手できます。
また、各地の商工会議所では事業計画書の作成をサポートしてくれるので、活用してみてはいかがでしょうか。
事業計画書を作成する際は、自身の店舗が焼肉屋として差別化できる理由を、具体的に記載することが重要です。アピールポイントとなるメニューやサービスなどを記載し、資金調達に役立てましょう。
資金を調達する
事業計画書が完成したら、金融機関などで資金調達の準備を始めましょう。焼肉屋の開業資金は、小さな店舗でも1,000万円程度は必要とされています。
収入が安定しない時期でも経営を続けるために、自己資金として3か月分の運転資金を貯めておくのがオススメです。
さらに、融資を受けたい場合は、自己資金を融資額の3分の1以上は貯めておく必要があります。具体的には、1,000万円の資金調達を目指すなら、少なくとも330万円以上の自己資金を用意しましょう。
資金調達の方法としては、以下の選択肢があります。
- 銀行からの融資
- 日本政策金融公庫からの融資
- クラウドファンディング
- 親族や友人からの借入れ
資金調達ができたら、物件の確保や内外装工事などの準備を進められます。しっかりとした資金計画を立てて、安定した経営基盤を築きましょう。
関連記事:飲食店は開業資金ゼロでも始められる?8種類の資金調達方法を徹底解説
資格取得の手続きを行う
焼肉屋を開業するためには、前述の「焼肉屋を開業する際に必要な資格・届出」を取得し、手続きを行います。
まず、食品衛生責任者の資格を取得します。飲食店営業許可を得る際に必要になるので、事前に取得しておきましょう。
次に、保健所での審査が必要です。店舗の完成図面ができた時点で、保健所に相談に行きます。保健所の担当者が図面を確認し、必要な修正があれば指示を受けます。その指示に従って修正を行い、再度保健所に提出してください。
最後に行うのは、営業許可の申請です。食品衛生責任者の資格を取得し、保健所の審査を通過した後に、営業許可の申請が可能になります。営業許可が下りれば、焼肉屋の営業を開始できます。
店舗の収容人数によっては、防火管理者の資格も必要です。
順を追って手続きを行い、抜け漏れがないようにしましょう。
参考:厚生労働省「一般的な営業許可手続きの流れ」
人材採用・教育を行う
焼肉屋を開業する際、成功のカギとなるのが人材採用と教育です。
焼肉屋は1人で運営するのは難しく、スタッフの協力が不可欠です。開店1か月前までにアルバイトを雇い、教育を終わらせておきます。
特に飲食店勤務経験者を雇うと、スムーズに業務が進みます。スタッフの採用・教育は、以下のポイントを押さえて行うのがオススメです。
- 調理や接客・衛生面に関するマニュアルを作成
- 食中毒や感染症の対策を重視
できるだけ人件費を抑えたい場合は、セルフオーダーシステムの導入を検討してみてもいいかもしれません。セルフオーダーシステムとは、スタッフを通さず、QRコードやタブレット端末などを用いて、お客様自身に注文・会計をしてもらうシステムです。
人手不足の強い味方であり、注文の伝達ミス防止にもつながります。
採用・教育のステップでは、可能な限り人件費を抑えつつ、高品質なサービスを提供するため準備を進めましょう。スタッフが円滑に業務をこなせれば、顧客満足度も高められます。
集客・宣伝を行う
人材採用・教育も終わり、いよいよ開店する準備が整ったら、集客のために宣伝を行いましょう。
まず、インターネットを活用して効果的に宣伝を行います。特にSNSは、費用を節約しながら大勢に情報を届けられるため、積極的に活用したいツールです。SNSで多く拡散されれば、短期間で高い集客効果が期待できます。
なかでも写真投稿がメインのInstagramでは、「映える」画像が注目されやすいです。Instagramには短時間の動画を投稿できるシステムの「リール」もあります。美味しそうな焼肉やサイドメニューのシーンを投稿できれば、視聴者が興味を持ってくれる可能性が高いです。
実際に、Instagramでの集客をメインにしている焼肉屋では、リール動画が40万回も再生され、集客に寄与しているケースもあります。
ターゲットの年齢層によっては、フリーペーパーやポスティングも効果的な選択肢です。地域密着型のフリーペーパーや、ポスティングを通じて近隣住民にアプローチすれば、確実に情報を届けられます。さらに、広告と一緒に割引券を配布すると、来店を促進できるでしょう。
お店の方向性に合わせて、SNSやフリーペーパーなどの方法を活用してみてはいかがでしょうか。
焼肉屋の開業で失敗しないポイント

ご自身の焼肉屋を構えられたら、できる限り早く軌道に乗せ、成功させたいところです。
この項目では、焼肉屋の開業で失敗しないためのポイントを、下記の4つにまとめました。
- 競合やターゲットを分析する
- 素材の品質を優先する
- 経営の知識を身に付ける
- 質の良い居抜き物件を選ぶ
それぞれ詳しくみていきましょう。
競合やターゲットを分析する
焼肉屋の開業で失敗しないためには、競合やターゲットの分析は欠かせません。
まず、競合店の魅力や独自性を分析しましょう。競合店の強みを理解すると、自店舗の改善点を見つけられるほか、差別化を図れます。
次に、店舗のコンセプトがぶれないように、ターゲットを明確に設定します。具体的には、どの客層がどのタイミングで利用するのかを考えましょう。
ターゲットが家族連れであれば、子ども向けのサイドメニューを充実させたり、アレルギー対応のメニューを盛り込んだりといった工夫が考えられます。また、ランチに来店してほしいのか、お祝い事で使ってほしいのかといった目的での設定でも、方向性が変わってくるでしょう。
競合やターゲットを分析し、独自の魅力を打ち出していきましょう。
素材の品質を優先する
経営のコストを削減したいからといって、素材の品質を下げてしまうのはオススメできません。
焼肉屋を開業する際に最も重要なポイントの一つは、提供する肉の品質です。高品質な肉を使用すると、顧客満足度が向上し、リピーターを増やせます。
反対に、低品質な食材を使用すると、すぐに悪い口コミが広まり、客足が遠のいてしまうでしょう。SNSやインターネットが活発な現代では、悪い口コミは想像以上のスピードで広まる可能性があります。悪い口コミをできる限り避けるために、コスト削減は素材以外の部分で行うのがオススメです。
素材以外でコストを削減するには、以下のような選択肢があります。
- 内外装のデザインをシンプルにする
- 宣伝費を効果的に使う
例えば「宣伝に注力したい!」という思いがあるなら、テレビコマーシャルなどの大々的な施策を打つよりも、SNSに注力したほうがコストパフォーマンスが良いケースもあります。
品質を維持しながら、無駄なコストを削減できるように、工夫してみてはいかがでしょうか。
経営の知識を身に付ける
焼肉屋を開業して成功するためには、経営の知識が欠かせません。利益を上げるためには、客単価と回転率についての理解が重要です。客単価と回転率は、以下の計算式で算出します。
- 客単価(お客様1人が1回に支払う金額)
=売上÷客数 - 回転率(お客様が1日に入れ替わる回数)
=客数÷客席数
客単価を把握しておけば、価格設定やマーケティングに役立ちます。
例えば、飲み放題メニューを提供したり、居心地の良い空間を演出したりすると、客単価を上げることが可能です。
また、回転率を上げるには、「メニュー数を減らす」「提供スピードを上げる」「オペレーションにかかる時間を短縮する」などの工夫が求められます。これらのポイントを押さえると、経営の効率を高められます。
客単価や回転率の知識を身に付けると、焼肉屋を経営していくうえで必要なデータが読み解けるようになり、成功に近づけるでしょう。
質の良い居抜き物件を選ぶ
焼肉屋の開業で思わぬトラブルを抱えないためには、質の良い居抜き物件を選ぶことが重要です。
居抜き物件とは、前のテナントが使っていた設備や内装が、そのまま残っている物件を指します。飲食店の開業時に居抜き物件を使うと、初期費用が大幅に節約できるため、人気が高い選択肢です。
しかし、居抜き物件には注意点もあります。
例えば焼肉屋の居抜き物件を借りたものの、設備に不具合があり火災リスクを抱えていた例もあります。
このような事態を防ぐために、古い設備は故障するリスクがある点を理解し、事前にしっかりと点検を行いましょう。また、以前のテナントの悪評が残っている可能性もあるため、口コミ・評判を確認しておきます。
質の良い居抜き物件を選ぶポイントは、下記の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:焼肉屋 居抜き
また、ラルズネットが提供する「テナント連合隊」では、焼肉屋の居抜き物件も掲載していますので、活用してみてはいかがでしょうか。
焼肉屋を開業するデメリット

焼肉屋を開業する前に、以下のデメリットも押さえておきましょう。
- 労働時間が長くなりやすい
- 開業資金が高い
- 食中毒のリスクがある
労働時間が長くなりやすい
焼肉屋を開業するデメリットの一つとして、労働時間が長くなりやすい点が挙げられます。
まず、肉の仕込みに時間がかかります。具体的には、肉の筋取りや臭み取りなどの作業が必要です。
また、焼肉屋は夜遅くまで営業している店舗も多く、閉店後の片付けや翌日の準備も時間がかかります。
さらに、サイドメニューを売りにしている場合、これらの仕込みにより多くの時間を要するでしょう。例えば、サラダやデザートの準備、特製タレの仕込みなどです。これらの作業が重なると、一日の労働時間は非常に長くなります。
労働時間を短縮するための対策として、以下の方法があります。
- メニューを簡素化する
- セルフレジを導入する
- 運搬ロボットを導入する
焼肉屋を開業する際には、労働時間の長さを考慮し、適切な対策を検討するのがオススメです。
開業資金が高い
開業資金が高い点も、焼肉屋を開業する際のデメリットです。
焼肉屋には排煙設備が必須ですが、費用が非常に高くなります。排煙設備の設置には、200万円以上かかるケースも珍しくありません。
あわせて、ロースターや冷凍冷蔵庫、コンロ・フライヤーなどの大型設備が必要です。これらの設備も高額で、初期投資の大部分を占めます。
さらに、小さい店舗の焼肉屋でも、開業資金として1,000万円以上かかるケースが多く、他の飲食店と比べて高額です。
焼肉屋の開業には高額な資金が必要なため、事前にしっかりと資金計画を立てることが重要です。
また、以下のような方法を使えば、費用を節約できます。
- 中古品を購入する
- リース契約を利用する
とはいえ、リース品は長期的にみると新品より総額が高くなるため、慎重に選択したいところです。
焼肉屋は開業資金が高いというデメリットを把握し、ご自身に合った対策を講じてみてください。
食中毒のリスクがある
最後に紹介する焼肉屋開業のデメリットは、食中毒のリスクです。焼肉屋では生肉や加熱不足の肉を扱うため、食中毒が発生する可能性が高まります。特に肉は傷みやすく、適切な保存や調理がされないと危険です。
もし食中毒を起こしてしまった場合、評判の低下は免れません。SNSや口コミで悪い評判が広まるほか、保健所からの指導により営業停止処分を受ける可能性もあります。
実際に、厚生労働省が公表する「令和4年食中毒発生状況」によると、食中毒の40%は飲食店で発生しています。学校や家庭・病院などでの発生に比べて、トップの数字です。傷みやすい生肉を扱う焼肉屋には、より一層の注意が求められます。
食中毒のリスクを最小限に抑えるためには、以下の対策が重要です。
- 衛生管理を行う
- 従業員の健康管理を行う
- 従業員に衛生教育を行う
衛生計画や管理日誌などを用いて、食中毒のリスクを抑えましょう。厚生労働省では、飲食店向けに衛生管理の手引を公開していますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。(参考:厚生労働省「HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き」)
焼肉屋を開業するメリット

前の項目では、焼肉屋を開業するデメリットを解説しましたが、一方で以下のメリットもあります。
- 幅広い年代に人気がある
- リピーターになってもらいやすい
- 客単価が高い
- フードロスが少ない
- 人件費を抑えやすい
それぞれ詳しくみていきましょう。
幅広い年代に人気がある
焼肉屋を開業するメリットの一つとして、幅広い年代に人気があることが挙げられます。
「J-Net21」の焼肉に関する市場調査をみると、焼肉屋の利用に受容的な態度を持つ(否定的な意見を持たない)人の割合は、ほとんどの年代で80%を超えています。
老若男女問わず愛される焼肉は、特定のターゲットに限られた業態に比べて、集客がしやすいです。以前はお祝いの席で食べられるイメージが強かった焼肉も、最近では手軽にランチとして楽しむ人が増えてきました。
また、一人焼肉も流行しており、さまざまなニーズに応えられます。具体的には、下記のような客層が見込めます。
- 家族連れ
- カップル
- 友人同士
- 一人客
多様な年代や客層からニーズがある焼肉屋は、集客のしやすさという観点からみると、成功する確率が高いです。
リピーターになってもらいやすい
リピーターになってもらいやすい点も、焼肉屋を開業するメリットです。
焼肉は比較的単価が高い料理であるため、お客様は「店選びに失敗したくない」という心理が働きます。そのため、一度気に入ったお店をみつけると、リピーターになってくれる可能性が高いです。
焼肉屋のリピーターを増やすには、以下の方法が挙げられます。
- スタンプカードやクーポンを活用する
- メルマガやSNSで定期的に情報を発信する
- 提供メニューのイチオシポイントを説明する
なかでも「提供メニューのイチオシポイントを説明する」項目は、自信のある品を提供するときに欠かせないアクションです。
「この焼肉屋の〇〇は、××という理由でこんなにも美味しい」というふうにお客様にインプットしてもらうと、記憶に強く刻まれるでしょう。反対に、「理由はわからないけど、なんとなく美味しい」という状態では、焼肉屋の記憶はぼんやりとしたものになり、リピート率向上は期待できません。
リピーターが増える工夫を行い、満足度の高いサービスを提供していけば、お客様はいつしかファンになってくれるはずです。
客単価が高い
焼肉屋を開業するメリットの一つは、客単価が高いことです。
お客様が複数の肉やサイドメニューを注文するケースが多いため、1人あたりの支出が自然と高くなります。さらに、お酒を頼むお客様も多いのも、客単価をさらに押し上げる要因です。
例えば、ラーメン屋と比べると、同じ集客力でも焼肉屋の方が圧倒的に稼ぎやすいです。ラーメン屋では1人あたりの注文がラーメン1杯に限られるケースが多い一方、焼肉屋では複数の肉料理に加え、サイドメニューや飲み物を注文するケースも多くあります。
焼肉屋の高い客単価を実現するためのポイントは、以下の通りです。
- お酒の品揃えを充実させる
- 団体客の割引を設ける
「団体客の割引を設ける」理由は、2人客より4人以上のお客様のほうが、盛り上がって次々に注文してくれる傾向にあるからです。大人数で焼肉屋に行きたくなる理由を作れば、客単価を上げられるでしょう。
高い客単価を維持し、安定した収益を出すために、さまざまなプランを立ててみましょう。
フードロスが少ない
焼肉屋は食材の無駄を抑えやすく、フードロスが少ない点もメリットです。焼肉屋で扱う肉は冷凍保存が可能なので、廃棄を抑えられます。食材の無駄が減れば、原価率ダウンが可能です。
また、他の飲食店に比べて使用する食材の種類が少ない点も、フードロスを減らす大きな要因です。例えばレストランでは多種多様な食材を使用するため、それぞれの鮮度管理が欠かせません。
一方で、焼肉屋で扱う食材は、主に肉と数種類のサイドメニューに集中します。そのため、食材管理が容易になり、無駄が出にくいです。
フードロスをさらに減らすための具体的な方法としては、以下のような取り組みが考えられます。
- 食べきれるような小分けのメニューを提供する
- 食中毒対策をしたうえで持ち帰りを推進する
- 料理の量を個人が選べるメニューにする
- 完食したお客様にインセンティブを提供する
「完食したお客様にインセンティブを提供する」取り組みでは、食べきってくれたお客様に対して、クーポンやポイントを付与します。完食したことで嬉しい特典があれば、「次回も食べきろう」と思ってもらえるでしょう。
「フードロスが少ない」という焼肉屋のメリットを最大限に活かせば、効率的な経営を実現できます。
人件費を抑えやすい
焼肉屋は「お客様が自分で肉を焼く」ため、人件費を抑えやすいです。
レストランでは、調理を行うシェフやキッチンスタッフが多く必要ですが、焼肉屋ではその必要がありません。通常のレストランと比べれば、調理に集中するスタッフが少なくて済むでしょう。
「労働時間が長くなりやすい」の項目で前述したように、運搬ロボットやセルフレジを導入すれば、さらなる人件費カットが可能です。
焼肉屋は他の飲食店と比べて、人件費を大幅に削減できる可能性が高いため、「多くのアルバイトは雇えそうにない」と悩んでいる方にとっては、メリットが大きいといえます。
焼肉屋の開業時によくある質問

この項目では、焼肉屋の開業時によくある質問をまとめました。
焼肉屋は儲かる?
政府統計の総合窓口が公表している「令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 売上(収入)金額等 」によると、焼肉屋の従業者1人当たりの年収は524万円でした。同データで飲食店全体の年収が447万円である点を考慮すると、焼肉屋は収入が高い業態です。
とはいえ、1店舗のみの場合は、年収は250~400万円程度ともいわれているため、一部の成功している焼肉屋が平均を押し上げている可能性もあります。
焼肉屋の開業で平均以上の収入を得るためには、1店舗目を成功させたうえで、多店舗展開していく姿勢が求められるでしょう。
焼肉屋の廃業率は?
「令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計産業横断的集計 事業所数、従業者数」によると、2021年に廃業した焼肉屋の事業所数は5,176件でした。もともと存続していた事業所数が13,788件だったため、廃業率は「5,176÷13,788=0.375」で約37.5%となります。
同データでの飲食店全体の廃業率は58.1%であるため、平均よりは数値が低い結果です。
とはいえ、株式会社帝国データバンクによると、2024年1~6月にかけて焼肉屋の倒産は急増しており、過去最多のペースといわれています。
ほかの外食の選択肢にも負けない魅力づくりが求められます。
参考:株式会社帝国データバンク「「焼肉店」の倒産動向調査(2024年1-6月)」
焼肉屋の開業時に物件を探すなら「テナント連合隊」!

焼肉屋の開業時には、小さな店舗でも1,000万円以上の初期費用が必要です。
スムーズに資金調達ができるように、市場調査やコンセプト・ターゲット設定を入念に行い、具体的な事業計画書を作りましょう。
焼肉屋の開業時にできる限り初期費用を抑えたいなら、居抜き物件という選択肢もあります。居抜き物件とは、前テナントが使用していた内装や設備がそのまま残っている物件です。
ラルズネットが運営する「テナント連合隊」では、焼肉屋の居抜き物件も掲載していますので、ぜひご活用ください。
貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。
路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。





 で
で